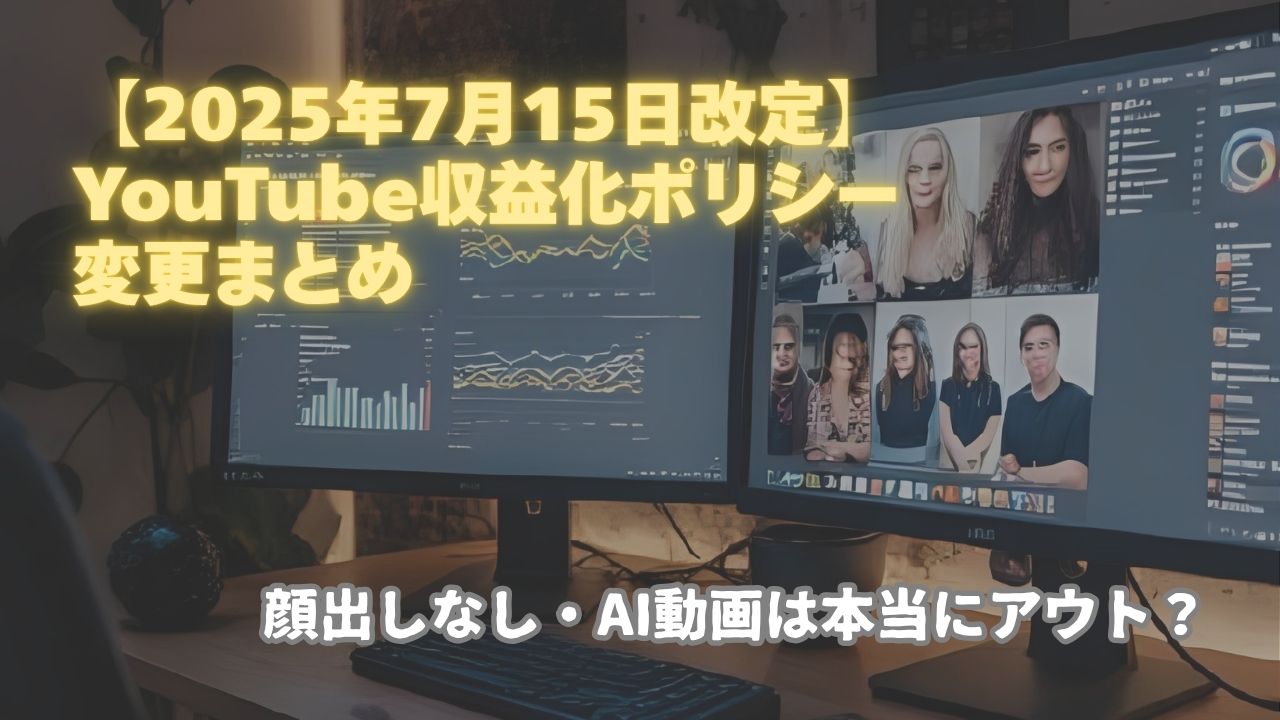2025年7月15日から、YouTubeの収益化ポリシーが大幅にアップデートされ、クリエイター界隈で注目が集まっています。「顔出しなしはもうダメ?」「AI使った動画は全部収益化停止?」といった憶測が飛び交っていますが、本当のところはどうなんでしょうか?
そこで、実際の変更内容を詳しく調べて、どんな動画が本当に影響を受けるのか、そして今後どう対応していけばいいのかをわかりやすく解説していきます。
YouTubeの収益化ポリシー変更:何が本当に変わったのか?
YouTubeのチャンネル収益化ポリシーの変更については、兎にも角にもヘルプをチェックしておくのがおすすめです。
まず最初に、今回の変更で一番大切なポイントを整理しておきましょう。ネット上で飛び交っている噂とは違い、実際の変更内容はそこまで極端なものではありません。
変更の核心は「大量生産・低品質動画」の排除
今回のアップデートで最も重要なポイントは、「オリジナルで本物のコンテンツ」であることが収益化の絶対条件として強化された点です。これまでの「再利用されたコンテンツ」という規定が「非本物コンテンツ」へと名称変更され、より厳格な審査が行われることになりました。
YouTube側の狙いは明確で、AI技術の発展によって大量生産される「スパム的な動画」を排除し、真正なクリエイターを保護することです。広告価値の低い低品質動画が蔓延することで、プラットフォーム全体の価値が下がるのを防ぐのが目的としています。
AI技術は「敵」ではない:適切な活用は今後も推奨
ここで重要なのは、今回の変更は「AI技術そのものを排除する」ことが目的ではないということです。YouTube関係者のコメントや公式声明を見ても、AI技術を効率化ツールとして適切に活用することは引き続き推奨されています。
問題となるのは、AIにすべてを任せきりにした「人間の創意工夫が感じられない動画」であり、AI技術を使いながらも独自性や付加価値を提供している動画は今後も収益化可能です。この点を誤解すると、必要以上にAI技術を避けてしまうことになりかねません。
誤解を解く:「顔出しなし」「AI利用」だけでは収益化停止にならない
ネット上では「顔出しなしは一律アウト」「AIを少しでも使ったらダメ」という噂が広がっていますが、これらは公式発表に基づかない憶測や誤解です。実際の公式ガイドラインでは次のような点が重視されています。
公式ガイドラインに基づく事実
- 顔出しの有無は原則関係なし
- AI技術の利用自体は問題なし
- 重要なのは「独自性」と「人間の創造性」があるかどうか
根拠のない噂に注意
- 「Vtuberは全員収益化停止」→ 事実無根
- 「ゆっくり解説は完全禁止」→ 内容次第で収益化可能
- 「AIツールを使うと即アウト」→ 使い方による
つまり、Vtuberだろうと、解説系YouTuberだろうと、顔を出さずにやっていても、オリジナルの価値を提供していればまったく問題ないということです。大切なのは、正確な情報に基づいて判断することですね。
本当に収益化停止になる動画の特徴とは?
それでは、具体的にどのような動画が今回の変更で影響を受けるのか見ていきましょう。
確実にアウトになるパターン
次のような動画は、今回の変更で確実に収益化が厳しくなります。
AI音声のみで構成された低品質動画
- ゆっくり解説やVOICEROIDなどのAI合成音声だけで、制作者の独自解説や工夫が一切ない動画
- テキスト読み上げのみで、付加価値がゼロの動画
テンプレート型の大量生産動画
- 毎回同じ構成で作られるランキング動画
- データや画像を入れ替えただけの使い回しコンテンツ
- セリフや演出が代わり映えしない量産型動画
他人のコンテンツの切り貼りメイン
- 映画やテレビ番組の映像をまとめただけの動画
- 他のYouTuberの動画を切り抜いて、最小限の解説しかつけていない動画
- 必要な解説や付加価値がないコンピレーション動画(他者の動画を切り貼りしてまとめただけの「○○シーン集」「ベスト10」など)
ストック素材頼りの自動生成コンテンツ
- フリー素材とBGMをAIツールでつなぎ合わせただけの動画
- AI生成キャラクターの口パクのみで内容が薄いな動画
- 人間の創意工夫が全く感じられないもの
収益化継続できる動画の特徴
一方で、次のような動画は引き続き収益化可能です。
独自性のあるVtuber・アバター系動画
- キャラクターを使っていても、制作者独自の演技や編集工夫がある
- 視聴者とのやり取りや個人的な体験談が含まれている
- オリジナルの企画やストーリー性がある
工夫された解説・教育系動画
- 顔出しなしでも、独自の視点や分析が含まれている
- 専門知識や経験に基づいた価値ある情報を提供している
- 視聴者のことを考えた丁寧な構成
クリエイティブな制作物
- アニメーション、音楽、アート系で独自性が高い
- AIツールを使っていても、人間の創造性が活かされている
- オリジナル要素が十分に盛り込まれている
具体例で理解する「セーフ」と「アウト」の境界線
ここまでの説明でもわかりにくい部分があると思うので、より具体的な例を使って境界線を明確にしていきます。実際のケースで考えると、判断基準がもっとわかりやすくなります。
アウトになりやすい具体例
例1:ニュース+掲示板反応まとめチャンネル
- ネットニュースの記事をAI音声で読み上げ
- その後に2chやYahoo!知恵袋の反応コメントをそのまま読み上げ
- フリー・ストック素材などの静止画や動画+BGM+AI音声のみの構成
- 制作者の分析や意見が一切なく、「ネットではこんな声が上がっています」程度のまとめのみ
例2:有名人のゴシップまとめチャンネル
- 「○○の炎上まとめ」として週刊誌やネットニュースの記事を転載
- AI音声で「ファンからは批判の声」「事務所は否定」などと事実を羅列
- サムネイルは毎回同じテンプレート(芸能人写真+衝撃的な文字)
- 記事の引用が90%以上で、独自取材や考察がゼロ
例3:ゲーム攻略コピペチャンネル
- 攻略サイトの情報をそのままAI音声で読み上げ
- 「レベル10で○○を装備してください」「ここでセーブしてください」と機械的に説明
- 実際にプレイしている映像はなく、ゲームのスクリーンショットを数枚使い回し
- 攻略サイトとまったく同じ情報で、実体験に基づくコツや失敗談が皆無
例4:都市伝説の量産チャンネル
- 「怖い話10選」「世界の不思議な話5選」などを毎日投稿
- ネットで拾った都市伝説をAI音声で読み上げるだけ
- フリー素材の怖い画像+ホラーBGMの定型パターン
- 「本当にあった話です」「信じるか信じないかはあなた次第」など決まり文句のみ
例5:雑学まとめの量産チャンネル
- 「驚きの豆知識10選」「知って得する雑学5選」を定期投稿
- Wikipedia や雑学サイトの情報をそのままAI音声で紹介
- 関連性のないフリー素材画像を適当に配置
- 「へぇ〜」「すごいですね」程度の薄いリアクションのみで、深掘りした解説や検証が皆無
セーフな例
例1:専門分野の解説動画
- 顔出しなしでも、その人ならではの専門知識がある
- 視聴者の質問に答える形式
- 個人的な経験や失敗談を交える
例2:創作系動画
- AIツールを使っていても、明確な作品性がある
- 制作過程での工夫や試行錯誤が見える
- 視聴者との交流を大切にしている
グレーゾーン:注意が必要なパターン
完全にアウトではないものの、収益化審査で厳しく見られやすいグレーゾーンのパターンもあります。
人間の声でも危険:口コミ読み上げ動画
「人が喋っているから大丈夫」と思いがちですが、実はそうではありません。たとえば次のような動画です。
- 「職場の愚痴を20件紹介します」として、ネット掲示板の投稿を人間の声で読み上げ
- 「このお店は美味しいと投稿されています」「評価が高いですね」程度のコメントのみ
- 口コミの内容が動画の90%以上を占め、制作者の分析や体験談がほとんどない
なぜグレーゾーンなのか?
YouTubeが重視するのは「声の種類」ではなく「コンテンツの価値」です。人間が喋っていても、他人の投稿をただ読み上げるだけでは「再利用コンテンツ」と判断される可能性があります。
グレーゾーンから脱出する方法
もし自分の動画がこのグレーゾーンに当てはまりそうなら、次のような工夫をすると収益化の可能性を高められます。
- 口コミの背景や社会的な意味を独自に解説
- 自分の実体験と照らし合わせた分析を追加
- 複数の口コミから見える傾向を考察として提示
- 視聴者への問いかけやQ&Aコーナーを設ける
楽観視は禁物:YouTube運営の現実を知っておこう
ここまで対策やセーフなパターンを解説してきましたが、あまり楽観視はしない方がいいと思います。それは「YouTubeの収益化ポリシーは、結局のところGoogleの判断次第」だからです。
ポリシーは予告なく変更される
今回の2025年7月の変更も、多くのクリエイターにとって突然の出来事でした。YouTubeは世界最大の動画プラットフォームとして、常に進化し続けています。そのため、今日「セーフ」だと思われていた動画でも、明日には新しいガイドラインで「アウト」になる可能性があります。
「グレーゾーン」は特に要注意
前述のグレーゾーンにある動画は、特に注意が必要です。現在は収益化できていても、次のアップデートで審査が厳しくなる可能性が高いからです。YouTube側の判断基準も、AIの進歩や市場の変化に応じて随時調整されています。
「完璧な対策」は存在しない
残念ながら、「これをやっておけば絶対大丈夫」という完璧な対策は、次のような理由により存在しません。
- 審査はAIと人間の両方が行っており、判断にブレが生じることがある
- 同じようなコンテンツでも、チャンネルによって審査結果が異なる場合がある
- 新しい技術やトレンドに対するポリシーは後追いで決まることが多い
長期的な視点で取り組む
だからこそ、小手先のテクニックに頼るのではなく、「本当に価値のあるコンテンツ」を作り続けることが最も確実な方法です。ポリシーがどう変わっても、視聴者に愛されるチャンネルは生き残っていけるはずです。
まとめ:本当に大切なのは「人間らしさ」と「価値提供」
今回のYouTube収益化ポリシー変更は、確かに一部のクリエイターには厳しいものかもしれません。しかし、本質的には「視聴者に価値を提供している真正なクリエイター」を守るための変更です。
顔出しするかどうか、AIを使うかどうかよりも、「あなたならではの価値」を届けられているかが今後は更に重要になってきます。この機会に、自分のチャンネルの方向性を見直してみるのも良いかもしれませんね。
AIが普及する時代だからこそ、人間らしい温かみや独自性が、これまで以上に価値を持つようになります。技術を上手く活用しながら、自分らしいコンテンツ作りが求められているということでしょう。