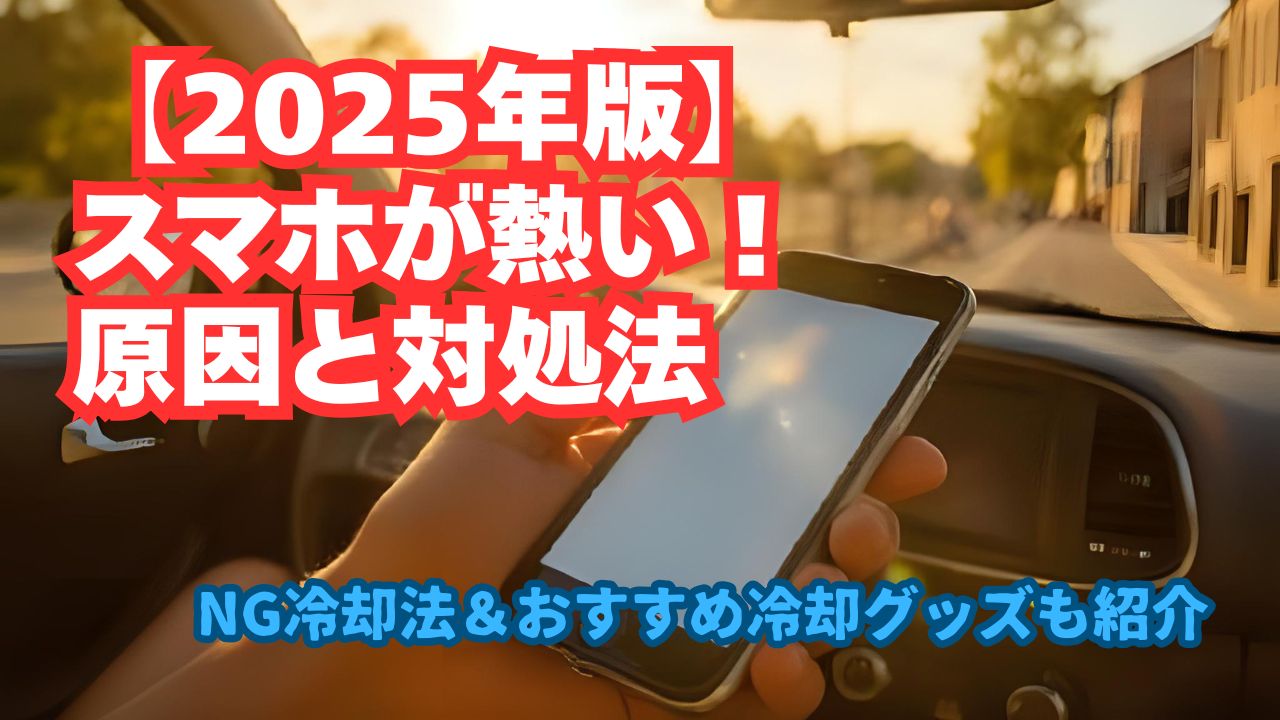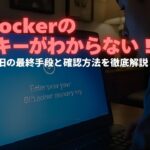夏場になると、スマホが熱くなって動作が重くなったり、最悪の場合は電源が落ちてしまうことがありますよね。特に動画撮影やゲームをしているときに「温度が高すぎます」という警告が出て、アプリが使えなくなったという経験をしたことのある人は多いのではないでしょうか。
私も夏の暑い日にビデオ撮影をしていたところ、わずか10分ほどで本体が熱くなり、録画が自動停止してしまったことがあります。
そこで、そんなスマホの熱問題について、原因から対処法、そして絶対にやってはいけないNG行為まで詳しく解説していきます。また、夏場でも快適にスマホを使うためのおすすめ冷却グッズも紹介したいと思います。
スマホが熱くなる主な原因
まず、なぜスマホが熱くなるのかを理解しておきましょう。主な原因を詳しく見ていきます。
高負荷な作業による発熱
長時間のゲームプレイや動画視聴、写真・動画の編集などは、CPUやGPUに大きな負荷をかけます。特に最新の3Dゲームや4K動画の再生は、想像以上に多くの処理能力を必要とするため、本体内部の温度が急激に上昇してしまいます。
例えば、重い3Dゲーム(「原神」や「PUBG Mobile」など)では、CPU使用率が80%超に達する場合もあり、海外の掲示板では「1時間ほどで端末がシャットダウンした」という報告も見られます。また、4K動画の撮影や編集、ARアプリの使用なども同様に高い負荷がかかる作業です。
充電しながらの使用
充電中にスマホを使用すると、バッテリーの充電による発熱と、アプリ使用による発熱が同時に発生します。これがダブルパンチとなって、本体温度を一気に押し上げる原因となります。
特に急速充電を使用している場合や、20W以上の高出力充電器を使用している際は発熱しやすくなります。ワイヤレス充電は有線充電よりもさらに熱を持ちやすい傾向があるので注意が必要です。
環境要因
直射日光の当たる場所での使用や、車内など高温環境に放置することも大きな要因です。多くのスマートフォンの動作温度は0℃から35℃程度とされており、これを超える環境では正常に動作しない可能性があります。
夏場の車内は50℃を超えることもあり、こうした環境にスマホを放置すると、「温度警告」が表示されて機能が制限されることがあります。また、直射日光下での長時間使用は、画面の明度も自動的に上がるため、さらに発熱してしまいます。
システムの問題
バックグラウンドで大量のアプリが動作していたり、ストレージ容量が不足していたりすると、システムが常に高負荷状態になります。また、バッテリーの劣化も発熱の原因となることがあります。
具体的には、ストレージ容量の残りが10%以下になると動作が重くなり、発熱しやすくなります。バッテリー最大容量が80%以下に劣化している場合も、通常よりも多くの電力を消費するため発熱の原因となります。OS更新直後やアプリの大量インストール時なども、インデックス作成などの処理で一時的に発熱することがあります。
熱くなった時の即効対処法
スマホが熱くなってしまった場合、以下の対処法を試してみてください。効果の高い順に紹介していきます。
最優先:使用を中止し、電源を切る
これが最も即効性の高い対処法です。アプリを終了するだけでなく、完全に電源を切ることで、CPUやGPUの動作を停止させ、発熱源を根本的に断つことができます。
iPhoneの場合は「音量ボタン(上または下)とサイドボタンを同時に長押し」、Androidの場合は機種により異なりますが、多くは「電源ボタンの長押し」で電源オフメニューが表示されます。
電源を切ることにためらう方もいるかもしれませんが、熱で本体にダメージを与えるリスクを考えると、一時的に電源を切る方がはるかに安全です。通常5〜10分程度で大幅に温度が下がり、安心して使用を再開できるようになります。
ケースやカバーを外す
スマホケースは保護には優れていますが、熱がこもりやすいというデメリットがあります。特に厚手のケースや革製のケースは放熱を妨げる可能性が高いので、熱くなったらすぐ外しましょう。
シリコンケースや手帳型ケースも要注意です。これらは密閉性が高いため、熱を内部に閉じ込めてしまいがちです。一方で、薄型のハードケースやメッシュ素材のケースは比較的放熱性に優れています。
ケースを外すだけで表面温度が5℃以上下がることも珍しくありません。ただし、ケースを外した状態では落下リスクが高まるので、安全な場所に置いて冷却することが大切です。
風通しの良い涼しい場所に移動
直射日光や暖房器具から離れ、エアコンの効いた室内など、涼しい場所に移動させます。可能であれば、扇風機の風が当たる場所や、日陰で風通しの良い場所を選びましょう。
机の上に置く際も材質に注意が必要です。熱伝導率の高い金属製のデスクは逆に熱がこもることがあるので避け、木製のテーブルや放熱性の良い材質の上に置くと良いでしょう。
屋外にいる場合は、建物の陰や車内のエアコンが効いている場所に避難することをおすすめします。車内に放置する場合は、ダッシュボードなど直射日光の当たる場所は絶対に避けてください。
エアコンや扇風機を使用する際は、直接風を当て続けるのは避けてください。スマホから30cm以上離すか、間接的に風が当たる場所に置くのがおすすめです。長時間の直風は結露や内部への異物侵入の原因となることがあります(詳しくは後述のNG行為を参照)。
充電を中断する
充電中の場合は、ケーブルを抜いて充電を停止します。急速充電機能を使用している場合は特に発熱しやすいので、本体が冷めるまで充電は控えることが大切です。
特に注意したいのがワイヤレス充電です。有線充電よりも効率が悪く、その分多くの熱が発生します。また、急速充電(Quick Charge、USB PD、MagSafe等)は短時間で大量の電力を送るため、必然的に発熱量も多くなります。
充電を中断することで、バッテリー周辺の温度が下がり、全体の冷却も促進されます。どうしても充電が必要な場合は、通常の充電速度(5W程度)に設定を変更するか、本体が十分に冷えてから再開しましょう。
バックグラウンドアプリを終了する
使用していないアプリがバックグラウンドで動作していると、知らず知らずのうちに負荷がかかっている場合があります。特にGPSを使用するアプリ、音楽ストリーミングアプリ、SNSアプリなどは常時動作していることが多いです。
iPhoneの場合はホーム画面で下から上にスワイプして、不要なアプリを上にスワイプして終了させます。Androidの場合は機種により異なりますが、多くは画面下部の「■」や「最近使用したアプリ」ボタンから操作できます。
一度に多くのアプリを終了させることで、CPUの負荷が大幅に軽減され、発熱も抑制できます。ただし、頻繁に使用するアプリまで終了させると、次回起動時により多くのリソースを消費する場合もあるので、バランスを考えて行いましょう。
機内モードを一時的に有効にする
通信機能(4G/5G、Wi-Fi、Bluetooth)を一時的に停止することで、さらなる負荷軽減が期待できます。特に電波状況が悪い場所では、スマホが電波を探すために余計な電力を消費し、発熱の原因となることがあります。
設定から機内モードをオンにするか、コントロールセンター(iPhone)やクイック設定(Android)から素早く切り替えることができます。
緊急時の連絡手段としてスマホを使う必要がある場合は、Wi-Fiのみをオンにして最低限の通信機能を確保することも可能です。この方法なら、モバイルデータ通信による発熱を抑えつつ、必要な連絡は取れるようになります。
機能オフ対策は本当に有効か?
よく紹介されるのが、「無駄な機能をオフにする」という対策です。しかし、今のアプリは多様な機能を使っていることが多いので、効果と利便性のバランスを考えることが重要です。結論から言うと、多くの方法は「効果はあるものの、日常の利便性を考えると割に合わない」というのが正直なところです。
バックグラウンド更新の制限
効果:★★★☆☆ 利便性への影響:★★★★☆
確実に負荷軽減効果はありますが、アプリの最新情報が取得できなくなるというデメリットがあります。特に困るのは、SNSアプリの通知が来なくなったり、天気アプリの情報が古いままになったりすることです。
普段あまり使わないアプリなら問題ありませんが、日常的に使うアプリまでオフにしてしまうと、「アプリを開くたびに読み込み時間が長い」「大事な通知を見逃す」といった不便さが目立ちます。
毎回設定を見直すのも面倒で、結果的に「熱くなった時だけ一時的に電源を切る」方が手軽で確実だと感じる方が多いのではないでしょうか。
位置情報サービスの見直し
効果:★★☆☆☆ 利便性への影響:★★★★★
GPSを使用するアプリを制限することで発熱予防に一定の効果はありますが、現代のスマホライフでは位置情報は必須機能です。
地図アプリが使えなくなったり、写真に位置情報が記録されなくなったり、お店の検索で「現在地周辺」が使えなくなったりと、日常生活への影響が大きすぎます。また、紛失時の「デバイスを探す」機能も使えなくなるため、セキュリティ面でもリスクがあります。
わずかな発熱抑制のために、これほど多くの利便性を犠牲にするのは現実的ではありません。
画面の明るさ調整
効果:★★☆☆☆ 利便性への影響:★★★☆☆
確かに画面の明るさを下げれば発熱は抑えられますが、屋外での視認性が大幅に低下します。「節電のために暗くしたけど、画面が見えなくて結局明るくした」という経験をお持ちの方も多いでしょう。
自動調整機能をオフにして手動で調整するのも、環境が変わるたびに設定し直すのが面倒です。「発熱対策のために画面が見づらい状態で我慢する」というのは本末転倒な気がします。
低電力モードの活用
効果:★★★☆☆ 利便性への影響:★★★★☆
全体的な動作が最適化されて発熱は抑えられますが、処理速度の低下やバックグラウンド更新の停止など、多くの機能が制限されます。
「バッテリーを長持ちさせたい時」には有効ですが、「発熱を抑えるため」だけに常時オンにするのは、スマホの性能を十分に活用できないもったいない状態と言えるでしょう。
現実的な対策の提案
これらの効果とデメリットを踏まえると、「日常的な設定変更よりも、熱くなった時の即効対処法を覚えておく方が実用的」というのが結論です。
具体的には次のような使い分けがおすすめです。
- 普段:特別な設定変更はせず、通常通り使用
- 熱くなったら:電源オフ→ケース外し→涼しい場所で冷却
- どうしても使い続けたい場合のみ:一時的に低電力モードや機内モードを活用
利便性を大きく損なう設定変更を常時行うよりも、「必要なときに適切な対処法を取る」方が、ストレスなくスマホが使えるのではないでしょうか。
絶対にやってはいけないNG行為
スマホが熱くなったとき、焦って間違った対処をしてしまうと、逆に故障の原因となる可能性があります。次の行為は絶対に避けてください。
冷蔵庫や冷凍庫に入れる
なぜダメなのか
「早く冷やしたい」という気持ちはわかりますが、これは最も危険な行為です。急激な温度変化により、内部で結露が発生し、水没と同じ状態になってしまいます。
スマホ内部の精密な電子部品は、温度差による結露に非常に弱く設計されています。40℃の本体を5℃の冷蔵庫に入れると、わずか数分で内部に水滴が発生し、ショートや腐食の原因となります。
実際に起きること
- 画面内部に水滴が見える「内部結露」
- スピーカーから音が出なくなる
- 充電ポートの腐食
- バッテリーの膨張
- 最悪の場合、完全に起動しなくなる
冷蔵庫から取り出した直後は一見正常に動作していても、数日後に突然故障するケースも多く報告されています。修理費用は数万円になることも珍しくありません。
保冷剤や氷を直接当てる
なぜダメなのか
保冷剤や氷を直接スマホ本体に当てることも、結露や水分侵入の原因となります。また、急激な温度低下により、内部の電子部品に熱応力がかかり、基板にクラックが入る可能性もあります。
特に注意したいのが「冷却スプレー」です。PC用の冷却スプレーをスマホに使用する方がいますが、これは非常に危険で、一瞬で内部結露を引き起こします。
「タオルで包めば大丈夫」「少し離せば安全」と考える方もいらっしゃいますが、これも推奨できません。わずかでも急激な温度変化を与えることに変わりはなく、リスクを完全に排除することはできないからです。
水に浸ける・水をかける
なぜダメなのか
「水に浸ければ冷える」と考える方もいらっしゃるかもしれませんが、これは完全にNGです。防水機能があるスマートフォンでも、熱による膨張で密閉性が低下している可能性があり、水没故障のリスクが非常に高くなります。
現在多くのスマートフォンが「IP68」などの防水等級を謳っていますが、これは「常温での清水への浸水」を想定したもので、高温状態での防水性能は保証されていません。
防水スマホでも危険な理由
- 熱膨張により、ゴムパッキンに隙間が生じる
- 内部圧力の変化で、防水シールが機能しなくなる
- 温度差による結露が防水機能では防げない
- 塩素や不純物を含む水道水は、純水よりも腐食リスクが高い
冷風を直接長時間当てる
意外な落とし穴
エアコンやドライヤーの冷風を直接当て続けるのも実は危険です。一見安全に思えますが、風量が強すぎると内部に塵やホコリが入り込んだり、スピーカーやマイクの穴から水分が侵入したりする可能性があります。
また、冷風といっても急激な温度変化には変わりないため、長時間当て続けると結露のリスクがあります。
正しい冷却方法
- 風は間接的に当てる(スマホから30cm以上離す)
- 連続使用は15分以内に留める
- ドライヤーの冷風よりも、扇風機の自然な風を推奨
アルコール系クリーナーで冷却
危険な民間療法
「アルコールは蒸発時に熱を奪うから」という理由で、除菌用アルコールやクリーナーをスマホに吹きかける方がいますが、これも危険な行為です。
アルコールは樹脂やゴム製品を劣化させる可能性があり、画面のコーティングを剥がしたり、ケースを変色させたりする原因となります。また、内部に浸透すると電子部品を損傷させる恐れもあります。
なぜNG行為をしてしまうのか
これらのNG行為に共通するのは「早く冷やしたい」という焦りです。しかし、スマートフォンは精密機器であり、急激な変化には対応できません。
大切な原則
- 「急激な温度変化は故障の元」
- 「自然冷却が最も安全」
- 「5分待てば十分効果がある」
これらの行為は、一時的に温度を下げることはできても、内部結露や部品損傷により、取り返しのつかない故障を引き起こす可能性があります。「急がば回れ」の精神で、安全な方法で自然冷却を待つことが最も確実で経済的です。
修理費用や買い替え費用を考えれば、数分間の我慢は決して高くない投資と言えるでしょう。
スマホ冷却を助けるおすすめグッズ
自然冷却だけでは不安な方や、夏場でも快適にスマホを使いたい方には、専用の冷却グッズがおすすめです。
| グッズ名 | 特徴・ポイント |
|---|---|
| スマホ冷却ファン | 背面に装着するだけで使用可能。即効性が高く、ゲームや動画撮影時に特に有効 |
| 冷却シート(スマ冷え等) | 貼るだけで熱を吸収し、薄型設計でケースとの併用も可能。繰り返し使用できる |
| スマホ用保冷剤(冷やスマ等) | 常温で使える専用保冷剤。ラバーバンドで簡単装着でき、繰り返し利用可能 |
| 放熱設計ケース | メッシュ素材やヒートシンク付きで、普段使いしながら熱対策ができる |
| MagSafe対応クーラー | iPhone 12以降の機種で使用可能。磁石で簡単装着でき、静音設計で高い冷却力を実現 |
このようなおすすめアイテムの中から、特に人気の高いアイテムを紹介していきます。多くのアイテムは現在開催中のAmazonプライムデーのセール対象になっているので、今なら安値で購入可能です。
ペルチェ素子搭載の高性能冷却ファン
Besecou F30は、ペルチェ素子を用いた急速冷却で、20秒以内にCPU温度を約15℃も下げることができる高性能な冷却ファンです。騒音値は30dB前後で、「ささやき声」のレベルに相当し、ゲーム中、ライブ中にも干渉しません。
1300mAhのバッテリーを搭載しており、フル充電で約90分使用することができます。USB給電しながらの使用も可能なので、長時間のゲームプレイや動画撮影でも安心です。伸縮式クリップで幅広い機種に対応している点も魅力的ですね。
RICQD スマホクーラーは、2025年の最新モデルとして登場したバッテリー駆動とUSB給電の2WAY対応という画期的な設計が特徴です。わずか3秒でひんやり冷却を体感でき、たった10秒でスマホ表面温度が10℃以上低下します。
MagSafe対応とクリップ式の両方に対応しており、iPhone 12以降の機種なら磁石で簡単に装着できます。LED温度表示も搭載されているので、リアルタイムでスマホの温度を確認できるのが便利です。
常温で使える特殊保冷剤
冷やスマPRO(a7987697)は、使用する際に冷蔵庫や冷凍庫で冷やす必要がなく、常温のままで効果を発揮する特殊な素材が使われています。結露が出ないという点。一般的な冷却材を使うとスマホに水滴がついてしまい、電子機器にとっては危険ですが、「冷やスマPRO」はその心配が一切ありません。
ゴムバンドでスマホに装着するだけで使用でき、電源も不要なので、外出先でも手軽に熱対策ができます。繰り返し使える経済性も魅力の一つです。
貼るだけで簡単!PCM素材の冷却パッド
エレコム P-SMPT02BU(モバピタッCool BIGサイズ)は、28℃以下で自然凍結するPCM素材を採用しており、約90分間冷却し続けられ、スマートフォンの温度を最大7.6℃下げます。
凍結していても結露しない素材で、水気によるスマートフォンの故障を防ぎます。また、W約49mm×H約74mmで、小型のスマートフォンでも背面カメラを覆わずに貼り付けできるコンパクトサイズです。
粘着面は何度でも貼り直しが可能で、使わない時は専用保管シートでホコリの付着を防げます。一度溶けても冷水に約10分つけるだけで冷却機能が復活するのは便利ですね。
バッテリー内蔵の大容量冷却ファン
サンワダイレクト 400-CLN027は、1800mAhのバッテリーを搭載。たっぷり長時間安心して使えます。ペルチェ素子冷却シートで熱を持ったスマートフォンを瞬間冷却するスマートフォンクーラーで、熱を持った箇所をピンポイントで冷やすことができます。
ホルダータイプではないので、手持ちでスマホに当てて使うスタイルです。バッグに入れて持ち運んでも邪魔にならない小型サイズで、約132gと軽量なのも魅力です。
DSBWAN スマホ冷却ファン 5000mAhは、5000mAhの大容量電池内蔵、7〜15時間使用可能です。スタンド機能も付いているので、動画視聴やWEB会議にも便利に使えます。最大伸縮幅80mm、すべてのモデルに適用可能で、大型のスマートフォンにも対応しています。
多機能スタンド一体型
Ulanzi スマホスタンド 冷却ファン付きは、スマホスタンドとスマホクーラーが一体化してるので本当に便利、PCで作業をする傍らスマホのソシャゲの周回をしたいってときに使ってますというユーザーレビューがあるように、スタンドと冷却機能を両立した製品です。
360°回転可能で高さ調整もでき、横置き・縦置き両方に対応しています。デスクワークをしながらスマホを冷却したい方には特におすすめの商品です。
商品選びのポイント
冷却グッズを選ぶ際は、次のポイントを考慮すると良いでしょう。
- 使用シーン:ゲーム用なら冷却ファン、日常使いなら冷却シートが便利
- 電源の有無:外出先で使うなら電源不要タイプやバッテリー内蔵タイプ
- 対応機種:お使いのスマホサイズに対応しているか確認
- 静音性:動画撮影や通話時に使うなら静音設計のものを選択
夏場の熱対策はもちろん、冬場でも充電しながらの使用や高負荷なアプリの使用時には発熱が問題になります。これらのアイテムを活用すれば、一年を通してスマホを快適に使えるかと思います。
まとめ:正しい暑さ対策で快適に乗り切ろう
スマホが熱くなった際の対処法について解説してきましたが、最後に簡単にまとめておきましょう。
最優先すべきは安全な冷却方法です。 使用を中止して電源を切り、ケースを外して涼しい場所で自然冷却を待つのが最も確実な方法です。
機能オフによる対策も有効ですが、「バックグラウンド更新」や「位置情報サービス」など、普段の使い勝手に大きく影響します。機能をオフにする場合は、あまり利用しない機能からオフにするのがおすすめ。利便性とのトレードオフになるので、あまり無理にオフにする必要はないと思っています。
そして何より大切なのは、冷蔵庫や氷を使った急激な冷却は絶対に避けることです。一時的な効果を求めて取り返しのつかない故障を招いてしまっては元も子もありません。
夏場でも快適にスマホを使いたい方は、専用の冷却グッズを活用することで、発熱を予防しながら使用することができます。用途や予算に応じて、自分に合ったアイテムを選んでみてください。
頻繁に熱くなる場合は、バッテリーの劣化や内部の故障が原因の可能性もあります。そのような場合は、無理に使い続けずに、メーカーサポートや正規サービスプロバイダでの診断を受けるのがおすすめです。
暑い夏でも、正しい知識と対策で、スマホを快適に使い続けていきましょう。