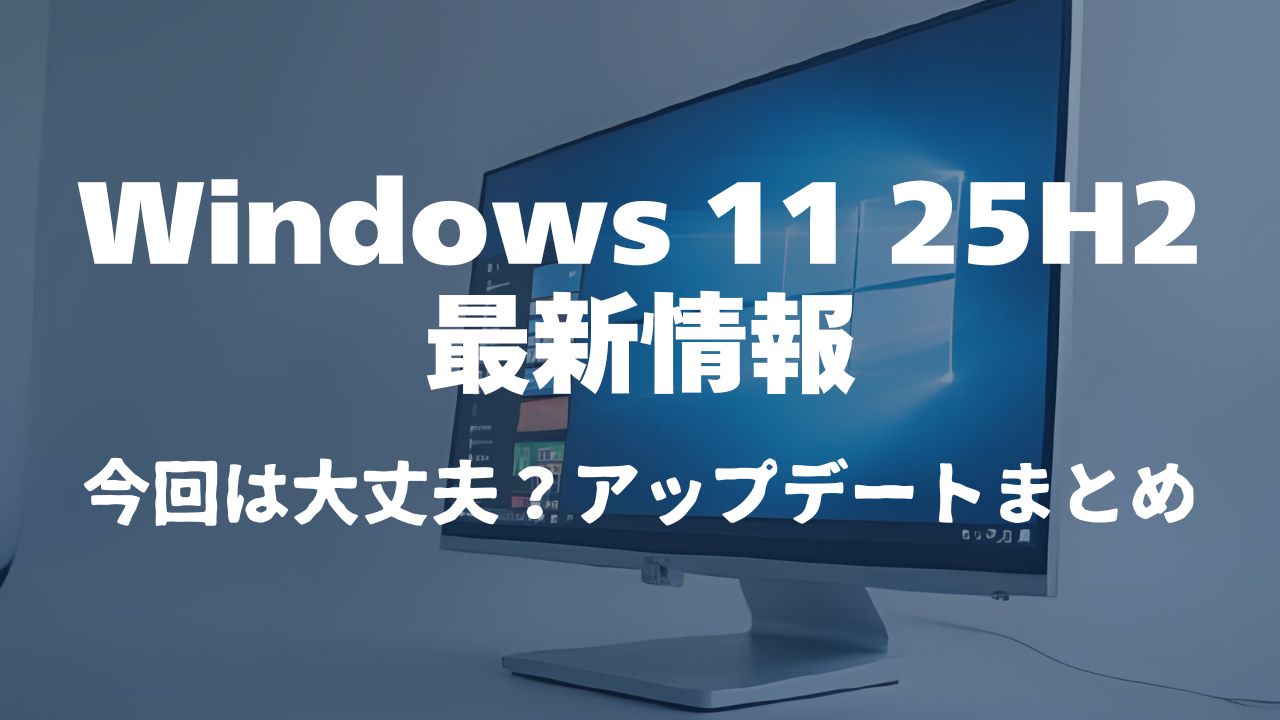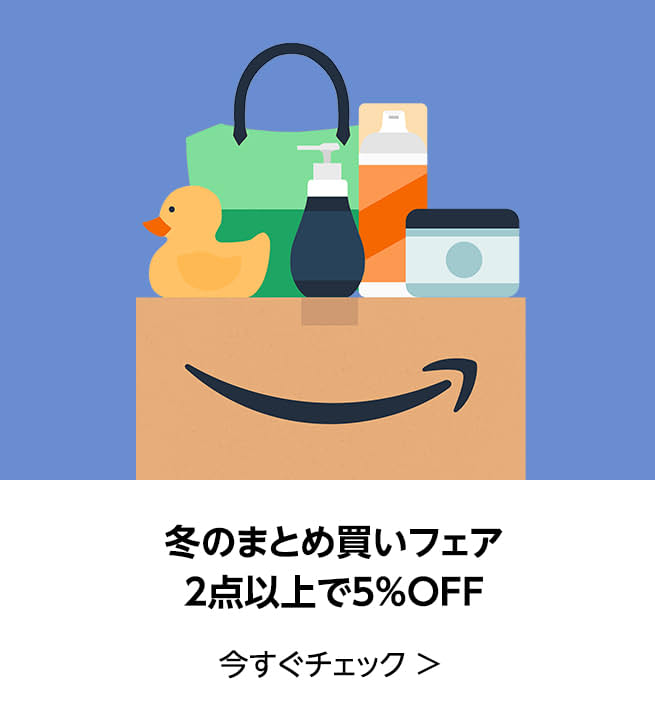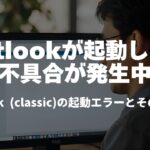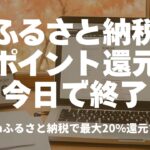2025年の秋、Windows 11に新しい大型アップデート「25H2」がやってきます。でも今回は少し様子が違うんですよね。派手な新機能がドカンと追加されるような従来のアップデートとは異なり、「安定性」と「使いやすさの向上」に重点を置いた内容になっています。
「結局何が変わるの?」「アップデートして大丈夫?」そんな疑問をお持ちの方も多いはず。そこで、Windows 11 25H2をできるだけわかりやすく解説していきます。
Windows 11 25H2って何?基本情報をサクッと理解
今回の25H2の最大の特徴は、「イネーブルメントパッケージ(eKB)」という新しい配信方式を採用していること。これは、従来のように大きなファイルをドカンとダウンロードするのではなく、既に24H2に含まれている機能を「有効化」するだけでアップデートが完了する仕組みです。
つまり、24H2を使っている方なら、再起動1回程度の短時間でサクッとアップデートできちゃうということですね。
Windows 11 25H2の配信スケジュールの予定は次のとおりです。
| 時期 | 内容 | 対象者 |
|---|---|---|
| 8月29日 | Release Preview公開 | Windows Insiderユーザー |
| 9月中旬 | 累積アップデート開始 | テストユーザー |
| 9月下旬~10月初旬 | 一般配信開始 | 全Windows 11ユーザー |
| 10月中 | 自動配信完了 | 全ユーザー |
新機能は…正直ほとんどありません
いきなり身も蓋もないことを言いますが、25H2では目立った新機能の追加はほとんどありません。複数のIT系メディアでも「新機能ゼロ」と報じられているほどです。
「え、それってアップデートする意味あるの?」と思われるかもしれませんが、実はこれがMicrosoftの戦略のようです。
なぜ新機能を追加しなかったのか
Microsoftは今回、「安定性」「互換性」「長期サポート」を最優先に考えたようです。過去のWindows Updateでは、新機能を詰め込みすぎて不具合が多発したり、既存のソフトが動かなくなったりするトラブルが頻発していましたからね(本当に酷いものでした)。
25H2は、そうした問題を解決するための「メンテナンス重視のアップデート」という位置づけです。企業や個人問わず、「安心して使い続けられるWindows」を提供することに重点を置いているというわけです。
削除される機能もあります
新機能追加がない一方で、一部の古い機能は削除されます。
- PowerShell 2.0:セキュリティ上の理由で廃止
- WMICコマンド:管理者向けツールの整理
これらは一般ユーザーにはほとんど影響がない部分なので、普通に使っている分には特に問題ないと思われます。
スタートメニューが大きく変わります
とはいえ、まったく変わらないというわけでもありません。25H2で最も大きく変更されるのがスタートメニュー。ただし、これは24H2から段階的に展開されてきた機能で、25H2で完全版になるという感じです。
新しいスタートメニューの特徴
新しいスタートメニューの特徴は次のとおりです。
1. 一体化されたデザイン
従来の「ピン留め」「おすすめ」「すべてのアプリ」が、スクロール可能な1つのページに統合されます。これにより、直感的に使えるようになっています。
2. おすすめセクションを非表示にできる
多くのユーザーから要望があった「おすすめセクションの非表示機能」が正式に追加されています。余計な情報を表示したくない方には嬉しい改善です。
3. 画面サイズに自動対応
使っているディスプレイのサイズや解像度に合わせて、スタートメニューが自動的に最適なサイズで表示されるようになります。
段階的な展開にご注意
25H2にアップデートしても、すぐに新しいスタートメニューが使えるとは限りません。今回、新しいスタートメニューは「A/Bテスト」という方式で段階的に配信されるため、最初は従来のデザインのままの可能性もあります。時間が経つにつれて徐々に新デザインに切り替わっていくので、気長に待ちましょう。
その他のUI改善点
スタートメニュー以外にも、細かなUI改善が施されています。
通知エリアの改善
- 時計表示の追加
- 通知センターの情報表示が強化
ロック画面のカスタマイズ強化
- パーソナライズオプションの拡充
- ウィジェット表示の改善
ダークモードの調整
- ファイルエクスプローラーのダークモード表示改善
- 設定アプリのデザイン調整
どれも地味な変更ですが、日常的に使う部分だけに、使い勝手の向上を実感できそうです。
安定性重視のメリットとは
今回の25H2が「安定性重視」と言われる理由と、そのメリットについて説明しますね。
アップデート時間が大幅短縮
25H2の大きなメリットの一つが、アップデート時間の短縮です。ただし、これには重要な前提条件があります。
24H2からのアップデートの場合
イネーブルメントパッケージ方式により、月例アップデート並みの短時間で完了します。再起動1回程度で済むため、「アップデートは時間がかかるから週末にやろう」なんて考える必要がありません。
23H2以前からのアップデートの場合
こちらの場合、23H2以前のバージョンからは従来通りの時間のかかるフルインストールが必要です。これは、24H2と25H2は同じ内部構造(共有サービスブランチ)を使用しているため、23H2とは互換性がないためです。
つまり、快適な短時間アップデートを体験するには、事前に24H2へアップデートしておく必要があるということになります。
互換性トラブルが激減
OSの基盤部分(Germanium)は24H2と同じものを使用しているため、既存のソフトやゲームとの互換性問題が起きにくくなっています。
「アップデートしたら使えなくなったソフトがある」というトラブルに悩まされることが少なくなるはずです。
企業での導入もスムーズ
安定性が重視されているため、企業でのIT管理者の方々も安心して導入を検討できます。長期サポートも継続されるので、運用計画も立てやすいでしょう。
アップデート時の注意点とトラブル対策
どんなに安定性を重視したアップデートでも、100%トラブルフリーとは限りません。ましてや、ここ最近のトラブルを目にしている人なら、いくら安定性が高いと言われても信じがたい人がほとんどだと思います。ですので、万が一に備えて、対策方法を確認しておきましょう。
事前準備
重要データのバックアップ
大切なファイルは外付けハードディスクやクラウドストレージにバックアップしておきましょう。
現在のバージョン確認
25H2は24H2からの軽量アップデートです。23H2以前のバージョンをお使いの場合は、まず24H2へのアップデートが必要になります。23H2から直接25H2にアップデートしようとすると、従来通りの時間のかかるフルインストールになってしまうので注意が必要です。
トラブルが起きた場合の対処法
復元期間の延長
アップデートして不具合が起きたら困りますよね。ですので、以前のバージョンに戻せる期間を延長しておくのがおすすめです。そうすれば、もし不具合が起きても元に戻せる猶予が長くなります。復元期間を延長する方法は、以下の記事で詳しく解説しているので、併せてご覧ください。
設定からの回復ツール利用
「設定」→「システム」→「回復」から、Windowsの問題解決ツールを実行できます。多くの問題はこれで解決できるはずです。
手動でのアップデート適用
自動アップデートが失敗した場合は、Microsoft公式サイトから手動でアップデートファイルをダウンロードして適用することも可能です。
UI変更による影響
スタートメニューの刷新により、普段使っているショートカットやランチャーアプリの設定に影響が出る可能性があります。アップデート後は、よく使うアプリが正常に起動するか確認してみてください。
まとめ:「地味だけど重要」なアップデート
Windows 11 25H2は、確かに派手さはありません。新機能の追加もほとんどなく、「つまらないアップデート」と感じる方もいるかもしれません。
でも、安定性と使い勝手の向上に重点を置いたこのアップデートは、実は非常に意味のあるものなんです。特に、仕事でPCを使う方や、トラブルを避けたい方にとっては、むしろ歓迎すべき内容と言えるでしょう。
とはいえ、最近のトラブル続きを見ていると、いまいち信頼できない部分があるのも事実です。そのため、特に急ぐ必要がないなら、様子見しても問題ないと思います。トラブルが潰されたタイミングを見計らって、アップデートするのが最も安全な運用方法のような気がします。