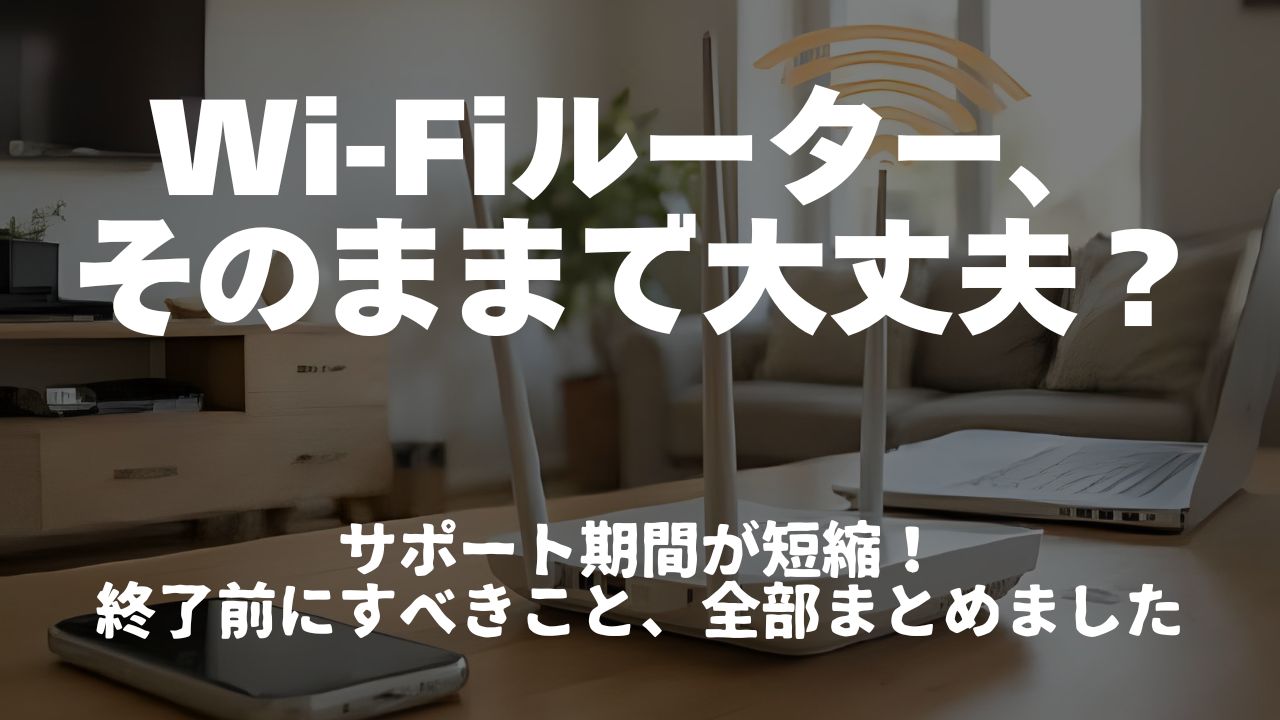自宅にあるWi-Fiルーター、いつ買ったものか覚えていますか?「まだ使えるから」と何年も使い続けている方も多いかもしれません。しかし、2025年12月から、国内大手メーカーのNECがAtermシリーズのサポート期間を大幅に短縮するという発表がありました。これはユーザーにとって、単なる「メーカーの都合」では済まない重要な変化なんです。
そこで、NECのサポート期間短縮の背景から、Wi-Fiルーターの安全な使い方、そして買い替えのタイミングまで、詳しく解説していきます。「セキュリティって難しそう」と思うかもしれませんが、実はユーザーの生活に直結する話なので、ぜひ最後まで読んでもらえると嬉しいです。
最新動向:NECのサポート期間短縮の背景
Atermシリーズのサポート期間が5年から3年に
2025年7月1日、NECプラットフォームズは人気のAtermシリーズについて、2025年12月1日から、これまで「販売終了から約5年間」としていたサポート期間を「販売終了から約3年間」へ短縮すると発表しました。
このような変更がされた理由について、NECはセキュリティに対する新たな脅威の増加を踏まえ、安心・安全かつ無線技術の急速な進化に即した製品へ注力することを目的としていると説明しています。つまり、新しいセキュリティ基準に対応した製品を提供するため、古い製品のサポートを早めに終了させる方針に転換したわけです。
他メーカーのサポート期間はどうなってる?
では、他のメーカーはどうなのでしょうか。各社のサポート期間を見てみましょう。
バッファロー
実は明確なサポート期間を定めていません。サポート期間の明確なガイドラインを設けておらず、セキュリティ問題が発生した際には販売終了製品も対象に含めて対処しているという方針です。2016年4月以降のモデルには自動ファームウェアアップデート機能があり、致命的な脆弱性が確認された際には自動的に更新されます。
エレコム・アイ・オー・データ
この2社も明確な期限を公表していませんが、実際には販売終了から数年でサポートが終了するケースが見られ、例えば2025年にはWi-Fi 5対応製品の多くがサポート終了となっています。
業界全体で「3年」が標準になるのか?
NECが業界大手としてこのような方針を打ち出したことで、今後は他メーカーも同様の短縮を行う可能性が高いと見られています。実際、サイバー攻撃の高度化や無線技術の急速な進化を考えると、3年という期間は決して短すぎるわけではないかもしれません。
ただし、これはユーザー側に「定期的な買い替え」を求めることにもなります。従来の「壊れるまで使う」という考え方から、「セキュリティを意識した更新」へと意識を変える必要がありそうです。
Wi-Fi 5/6/7の規格と世代別のサポート終了タイミング
それぞれの規格はいつ登場した?
Wi-Fiの規格は世代ごとに進化してきました。現在主流となっている規格とその登場時期を整理してみましょう。
Wi-Fi 5(IEEE 802.11ac)は2013年に解禁され、Wi-Fi 6(IEEE 802.11ax)は2019年に解禁、Wi-Fi 6Eは2021年2月にスタートしました。そして最新のWi-Fi 7は2023年12月に総務省により認可され、2024年から対応製品が登場し始めています。
サポート終了が進むWi-Fi 5とWi-Fi 6
2025年にサポート終了したWi-Fi 5対応製品として、バッファローのWSR-2533DHP2(2025年2月終了)、エレコムのWRC-2533GST2SP(2025年8月)、NECプラットフォームズのAterm WG2600 HP3(2025年8月終了)などがあります。
Wi-Fi 5世代の製品は、2013年前後に登場してから約10年以上が経過しており、多くの製品がすでにサポート期間を終えつつあります。一方、初期のWi-Fi 6対応製品も2026年1月からサポート終了の機器が登場し始める見込みです。
たとえば、エレコムのWRC-X3000GSは2025年8月に、バッファローのハイエンドモデルWXR-5950AX12も2026年1月にサポート終了予定となっています。「Wi-Fi 6だからまだ安心」という考えは、もう通用しなくなりつつあります。
現行モデルの状況
現在販売されている製品の多くは、Wi-Fi 6またはWi-Fi 6E対応モデルです。Wi-Fi 7対応製品も徐々に増えてきていますが、価格がまだ高めで、対応する端末(スマホやPC)も限られています。
購入する際は、単に「最新規格」だけでなく、実際に使用する端末が対応しているかも確認することが大切です。例えば、2025年8月時点で、13〜14インチサイズのノートPCでWi-Fi 6E対応は約78%、Wi-Fi 7対応は約15%という状況です。
とはいえ、今後発売するデバイスは、Wi-Fi 7対応が主流になっていくでしょう。なので、今持っていないからといって「自分にWi-Fi 7は関係ない」と考えるのは早計です。
メーカーサポートの内容とは?ルーターの「安全寿命」を考える
ハードウェアとソフトウェアのサポートの違い
メーカーサポートには大きく分けて2つの側面があります。
ハードウェアサポート
故障時の修理対応です。サポート期間中は、Atermインフォメーションセンターへの電話やメールでの問い合わせを受け付け、故障の場合は修理を受け付けるとされています。ただし、Wi-Fiルーターの場合、修理費用を考えると新品を買った方が安いことがほとんどです。
ソフトウェアサポート
こちらがより重要で、ファームウェア(ルーターのOS)の更新を提供することを指します。新たな脆弱性が発見された際に、それを修正したファームウェアが提供されるかどうかが、セキュリティの要となります。
ファームウェアアップデートと脆弱性対応
ファームウェアを更新することで脆弱性をなくすことができ、更新プログラムが提供されたら自動的に更新されるようになっていれば問題ないとされています。実際、最近のルーターには自動アップデート機能が搭載されているものも多いです。
しかし、サポート期間が終了すると、新たな脆弱性が見つかってもファームウェアが提供されなくなります。これが最大のリスクです。
サポート終了後に生じるリスク
サポートが終了したルーターを使い続けると、どんなリスクがあるのでしょうか。
脆弱性の悪用
セキュリティの穴が放置されることで、攻撃者に侵入される可能性が高まります。Wi-Fiルーターが乗っ取られると、VPN機能設定や見慣れないVPNアカウントの追加、DDNS機能設定など、ユーザーの知らないうちに設定が変更されてしまうケースがあります。
不正利用への加担
家庭用ルーターが外部から不正に操作されて、攻撃者によって遠隔操作され、DDoS攻撃など別の攻撃に使われてしまう可能性もあります。つまり、自分のルーターが知らない間にサイバー犯罪の踏み台にされてしまうわけです。
個人情報流出のリスク
ルーターを通じて、家庭内のスマート家電やパソコンに保存されているデータが外部に漏れる危険性もあります。防犯カメラの映像が見られてしまうなど、考えるだけで怖いですよね。
公的機関のアドバイス・注意喚起
警視庁・IPAからの警告
実は、公的機関も家庭用ルーターのセキュリティについて積極的に注意喚起を行っています。
警視庁は2023年3月に「家庭用ルーターの不正利用に関する注意喚起」を発表し、従来の対策のみでは対応できない新たな攻撃手法が確認されたと警告しました。具体的には、一度設定を変更されると従来の対策のみでは不正な状態は解消されず、永続的に不正利用可能な状態となるという、かなり深刻な内容です。
警視庁が推奨する対策は次の通りです。
- 初期設定の単純なID・パスワードを複雑なものに変更する
- 常に最新のファームウェアを使用する
- サポートが終了したルーターは買い替えを検討する
- 見覚えのない設定変更がなされていないか定期的に確認する
実際の被害事例
2024年5月に情報通信研究機構(NICT)が、家庭用Wi-FiルーターがMirai(ミライ)というマルウェアに感染しているのを発見しました。このマルウェアは、感染した端末を攻撃者が遠隔操作して、DDoS攻撃などに利用するものです。
怖いのは、マルウェアがルーターに感染しても、パソコンやスマホなど家庭の機器は問題なくインターネットに接続ができるため、家庭の利用者が問題に気づくことが難しいという点です。知らない間に加害者になってしまう可能性があるんですね。
また、仮にルーターが不正利用されて乗っ取られた場合、ルーターを介して接続している全てのIoT機器がコントロールされる可能性もあるとされています。スマート家電が多い家庭ほど、リスクも大きくなるわけです。
安全診断ツール「am I infected?」の使い方と実用性検証
サービス概要と運営団体
ここまで読んで「うちのルーター、大丈夫かな?」と心配になった方もいるかもしれません。そんな方におすすめなのが、横浜国立大学 情報・物理セキュリティ研究拠点 吉岡研究室が運営する無料のマルウェア感染・脆弱性診断サービス「am I infected?」です。
国立研究開発法人情報通信研究機構や総務省から委託を受けて行った研究の成果を広く社会に還元する目的で運営されているため、費用は一切かかりません。
利用方法(スマホ・PC共通)
使い方はとても簡単です。
- 自宅のWi-Fiに接続した状態で、「am I infected?」(https://amii.ynu.codes/)のウェブサイトにアクセス
- メールアドレスや使用環境、サービスを知った経緯などを入力し、「感染診断をはじめる」をクリック
- 5分以内に登録したメールに検査結果が送信される
- メール内のリンクから診断結果を確認
所要時間は1分程度で、特別な知識も必要ありません。
診断内容と判定基準
感染有無の診断は、横浜国立大学が運用しているおとりサーバ(ハニーポット)とNICTが運用するNICTERのデータを利用しているそうです。具体的には、診断を依頼したルーターのIPアドレスから、過去24時間以内に不審な通信が観測されていないかをチェックします。
診断結果としては、次のようなパターンがあります。
- 安全な状態:マルウェア感染や脆弱性が検出されなかった場合
- 脆弱性あり:ルーターのファームウェアが古い、またはセキュリティ上の問題がある場合
- マルウェア感染の疑い:不審な通信が観測された場合
注意点:診断の限界を知っておこう
ただし、このサービスにも限界があります。
診断の精度は完璧ではなく、見逃しや誤検知が発生することがある。仮に機器がマルウェアに感染していても、直近24時間以内に不審な通信が観測されていなければ感染を検知することができないため、定期的(月に1度程度)に確認することが推奨されています。
また、ルーターの先にあるホームネットワークにつながっているパソコンや防犯カメラ、プリンタなどの感染については検知は可能だが、どの機器が問題かを示すことはできないという制限もあります。
使っているメーカーのサポートを確認する
「am I infected?」以外にも、メーカー各社が提供している診断ツールやサポートページを確認するのもおすすめです。日本の主流メーカーだと次のページです。
- バッファローの「商品サポート状況一覧」でサポート状況を確認
https://www.buffalo.jp/support/other/product_support_status_list.pdf(PDF) - NECプラットフォームズの「Atermのサポート期間について」で自分のモデルを検索
https://www.aterm.jp/support/inquiry/hoshu_list.html - エレコムの「サポート終了・終了予定リスト」で確認
https://www.elecom.co.jp/support/end-of-support/
定期的に使っているメーカーのサポートページをチェックすることで、自分のルーターがいつまでサポートされるのかを把握できます。
買い替えのタイミングと選び方のポイント
「寿命3年」の目安の正しい使い方
NECのサポート期間短縮により、「ルーターの寿命は3年」という認識が広がりつつあります。しかし、これは正確には「販売終了から3年」であって、「購入から3年」ではありません。
例えば、2025年に購入したルーターでも、そのモデルの販売が2024年に終了していれば、2027年にはサポートが終了することになります。購入時に「このモデルはいつ発売されたか」「いつまで販売されているか」を確認することも大切です。
ただし、一般的な目安として考えると、日々報告される脆弱性問題に対してセキュリティを確保し、本来持つ性能を十分に発揮させ、より安全に使うため、最新の製品への買い替えが推奨されています。購入から5年以上経過している場合は、特に注意が必要でしょう。
どんな場合に買い替えを検討すべきか
次のいずれかに当てはまる場合は、買い替えを検討した方が良いタイミングです。
セキュリティの観点
- サポート期間が終了した、または終了が近い
- ファームウェアの更新が1年以上提供されていない
- 「am I infected?」で問題が検出された
- WPA2以前の古い暗号化方式しか対応していない
性能の観点
- Wi-Fi 5以前の規格しか対応していない
- 接続が不安定になることが増えた
- 通信速度が遅いと感じることが多い
- 同時接続する機器が増えた(スマート家電など)
利用環境の変化
- リモートワークが始まり、ビデオ会議が増えた
- 家族が増えて接続機器が増加した
- より高速なインターネット回線(光回線の10Gコースなど)に変更した
新規購入時の注目ポイント
新しいルーターを選ぶ際は、次のポイントに注目しましょう。
規格
現時点(2025年)では、Wi-Fi 6E対応モデルがバランスが良くおすすめです。ただし、今後の主流はWi-Fi 7になっていくのは間違いないので、将来を見据えるならWi-Fi 7を選んでもいいかもしれません。
セキュリティ機能
- 自動ファームウェア更新機能の有無
- WPA3対応(最新の暗号化規格)
- 初期パスワードが機器ごとに異なるか(固有化されているか)
サポート体制
- メーカーのサポート方針(明確な期間が示されているか)
- 過去の脆弱性対応の実績
- ユーザーレビューでのサポート対応の評判
その他の機能
- ビームフォーミングやMU-MIMOなど、複数台接続に強い機能
- 接続台数の上限(家族の人数や機器の数に合わせる)
- メッシュWi-Fi対応(広い家の場合)
個人的には「eero」を使ってます
今、自宅のWi-FIルーターには「eero」を使っています。これはAmazonがプッシュしているルーターで設定が簡単でコスパが良いというメリットがあります。確かに国内メーカーのルーターと比較すると、設定は非常に簡単。また、同じシリーズを追加すればメッシュWi-Fiにできるので、拡張性も高いのがいい点です。
Wi-Fi 7に対応した「eero 7」については、以下の記事で解説していますので、よかったらご覧ください。
なお、eeroはAmazonで定期的にセールしていますので、気になった方はチェックしてみてください。


まとめ
Wi-Fiルーターは「一度設置したら終わり」という機器ではなく、定期的なメンテナンスや買い替えが必要な「セキュリティ機器」として考える時代になってきました。
少し面倒に感じるかもしれませんが、自分や家族の個人情報を守り、知らない間にサイバー犯罪の加害者にならないためには、必要な対策です。この記事で紹介した内容を参考に、ぜひ一度ご自宅のWi-Fi環境を見直してみてください。
「セキュリティ対策って難しそう」と思っていた方も、できることから始めてみませんか?まずは「am I infected?」でチェックするだけでも、大きな一歩になると思います。