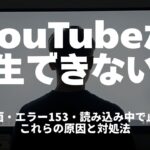2025年1月から、Microsoft 365にAI機能「Copilot」が標準搭載され、大幅な値上げが実施されました。しかし、多くのユーザーが知らないのは、実は「AIなし」で旧価格のまま利用できる「クラシックプラン」が存在するということなんです。
この「隠れプラン」問題は、オーストラリアではついに公的機関による調査・返金対応にまで発展する事態となりました。そこで、この選択肢不透明問題の実態と、私たちユーザーが知っておくべきポイントについて詳しく解説していきます。
そもそも何が起きているのか?
2025年1月、Microsoftは個人向けMicrosoft 365プラン(PersonalとFamily)にCopilot機能を標準搭載し、約45%という大幅な値上げを実施しました。例えば、Microsoft 365 Personalの場合、従来の年額14,900円から21,700円へと跳ね上がったわけです。
ところが、この値上げに伴い、「AIは不要だから旧料金で使い続けたい」というユーザー向けに「クラシックプラン」が用意されていました。この情報、当サイトでも解説していたのですが、あまり知られていないようですね。
この「クラシックプラン」なら、Copilot機能は使えないものの、Word、Excel、PowerPointといった基本的なOfficeアプリは従来通りの料金で利用できます。
問題は、このクラシックプランの存在が極めてわかりにくいという点です。Microsoftの公式サイトや更新通知メールを見ても、このプランの選択肢はほとんど表示されません。多くのユーザーが知らないまま、高額なCopilot付きプランに自動移行されてしまっているんですね。
どうやって「隠されている」のか?
具体的にどのような仕組みで隠されているのか、見ていきましょう。
通常、Microsoft 365の契約更新や新規契約を行う際、公式サイトでは「Microsoft 365 Personal(Copilot付き)」と「Microsoft 365 Family(Copilot付き)」の2つのプランが大きく表示されます。しかし、クラシックプランの選択肢は同じ画面には登場しません。
実は、クラシックプランへの案内が表示されるのは、解約手続きやキャンセル手続きを進めた場合のみなんです。つまり、「もう契約しません」という操作をして初めて、「それなら安いプランはいかがですか?」という形で提示される仕組みになっています(携帯キャリアで解約を伝えたら安いプランが提示されるようなものですね)。
あと、アリバイ作り的な感じで、こっそりとヘルプにも記載されています。しかし、このページを見つけること自体が大変です。
海外のフォーラム(Redditなど)では、この仕組みが「ダークパターン」(ユーザーを不利な選択に誘導するデザイン手法)に近いと批判されています。日本でも、Impress Watchなどの技術メディアが「クラシックプランへの変更方法」を解説記事として取り上げるほど、わかりにくい状況となっています。
サブスクリプションサービスでは、自動更新が基本設定になっていることが多いですよね。Microsoft 365も例外ではなく、何もしなければ自動的に新しい料金プランに移行してしまいます。ユーザーが積極的に情報を探さない限り、選択肢があることすら知らないまま高額プランを契約してしまう可能性が高いわけです。
ユーザーにとって何が問題なのか?
この状況は、ユーザーにとって複数の問題を引き起こしています。
まず、透明性の欠如です。サブスクリプションサービスを選ぶ際、私たちは複数のプランを比較して、自分に最適なものを選びたいですよね。しかし、選択肢の一つが実質的に隠されている状態では、適切な比較検討ができません。
次に、情報格差の問題があります。ITニュースサイトやテック系のフォーラムを日常的にチェックしているユーザーなら、クラシックプランの存在を知る機会があるかもしれません。しかし、そうした情報に触れる機会が少ない一般ユーザーは、不利な選択を強いられることになります。
さらに、実質的な価格の不透明さも問題です。Copilotを使わないユーザーにとっては、約7,000円の追加料金は単なる負担増でしかありません。「AIが必要ないなら旧プランで」という選択肢を明示しないまま料金を請求するのは、消費者にとって公平とは言えないでしょう。
ダークパターンと呼ばれるUI設計手法は、ユーザーを企業にとって有利な選択に誘導するものです。今回のケースも、解約画面でしか代替プランを提示しないという設計は、この手法に近いと指摘する声が上がっています。
オーストラリアでは公的機関が動いた
この問題が最も深刻化したのがオーストラリアです。2025年10月、オーストラリア競争・消費者委員会(ACCC)は、Microsoftが約270万人のユーザーに対して適切な説明を行わず、選択肢を隠蔽したとして提訴しました。
ACCCは、Microsoftが次のような問題のある対応を行ったと指摘しています。
- 値上げの通知メールで、クラシックプランの存在を明示しなかった
- 公式サイトでの新規契約・更新手続きで、クラシックプランを選択肢として提示しなかった
- 解約手続きを進めない限り、代替プランの案内が表示されない設計になっていた
この提訴を受けて、Microsoftは公式に謝罪し、対象となる約270万人のユーザーへの返金対応を発表しました。また、今後はよりわかりやすい形で全プランを提示すると約束しています。
この動きは世界中に波及し、「自分も知らないうちに高額プランにされていないか?」と確認するユーザーが増えています。ReutersやYahoo!、ABC Newsなど、主要メディアも相次いでこの問題を報道しました。
日本でも同じ仕組みが存在しているため、オーストラリアでの対応を知った日本のユーザーの間でも関心が高まっています。
ただ、昔からMicrosoftは日本市場に対しては対応が悪い/雑な感じが否めません。Windows 3.1の頃からMicrosoft製品を使っていますが、日本だけ対応が遅い、値段が高いといったことが割と多い印象です。特にOffice関連はトラブルを放置するといった対応の悪さも印象に残っているので、日本では役所あたりが動かない限り、何もしないんじゃないかなぁという感じはします。
日本のユーザーができること
では、日本のMicrosoft 365ユーザーは、どのように対応すればよいのでしょうか。
現在の契約内容を確認する
まず、自分が現在どのプランを契約しているのか確認しましょう。Microsoftアカウントの「サービスとサブスクリプション」ページにアクセスすると、現在の契約内容が表示されます。
もし「Microsoft 365 Personal」や「Microsoft 365 Family」と表示されていて、Copilot機能を使っていない、あるいは必要としていないなら、クラシックプランへの変更を検討する価値があります。
クラシックプランへの変更方法
クラシックプランに変更するには、残念ながら一度解約手続きを進める必要があります。具体的な手順は以下の通りです。
- Microsoftアカウントにサインインし、「サービスとサブスクリプション」を開く
- Microsoft 365の「管理」をクリック
- 「キャンセル」または「自動更新をオフにする」を選択
- 理由を選択する画面で、適切な理由を選ぶ
- この時点で「Classic」プランの案内が表示される場合がある
- クラシックプランに切り替える
ただし、この手順は変更される可能性がありますし、タイミングによっては表示されない場合もあります。
Copilotが本当に必要か見極める
クラシックプランへの変更を検討する前に、Copilotが本当に必要かどうか考えてみることも大切です。
Microsoft 365のCopilotは、文書作成の補助やデータ分析など、確かに便利な機能を提供します。しかし、月60回までという利用制限もありますし、すべてのユーザーにとって7,000円分の価値があるかというと、そうとは限りません。
個人的にCopilotを使っていて思うのは、他の生成AIと比較すると融通が効かないというか、あまり賢くない印象です。狙った答えが出る確率が低く感じるんですよね。ですので、普段はAIは外部サービスを使いながらOfficeアプリで編集するというケースが多いです。もしこのような使い方をしているのであれば、正直Copilotは必要ではありません。
「試しに使ってみたけど、結局あまり使わなかった」という方は、クラシックプランへの変更を検討する価値があります。
まとめ:選択の自由を守るために
Microsoft 365のクラシックプラン隠蔽問題は、デジタルサービスにおける消費者の選択の自由がいかに脆弱かを示しています。
Copilotは確かに便利な機能ですが、すべてのユーザーが必要としているわけではありません。AIを使わないユーザーが、AIの開発コストを負担させられるのは理不尽ですよね。選択肢があるなら、それを明確に示すのが企業の責任です。
日本のユーザーも、この問題を他人事と考えず、自分の契約内容を確認してみることをおすすめします。もしCopilotを使っていないなら、クラシックプランへの変更を検討する価値は十分にあるでしょう。
オーストラリアでの公的機関の対応は、消費者保護の観点から画期的なものでした。日本でも、こうした問題に対する監視の目が強まることを期待したいです。
サブスクリプションサービスは便利ですが、「自動更新だから楽」というメリットの裏には、こうした落とし穴が潜んでいることも忘れてはいけません。消費者は、自分にとって本当に必要なサービスを、適切な価格で利用していくことが大切ですね。