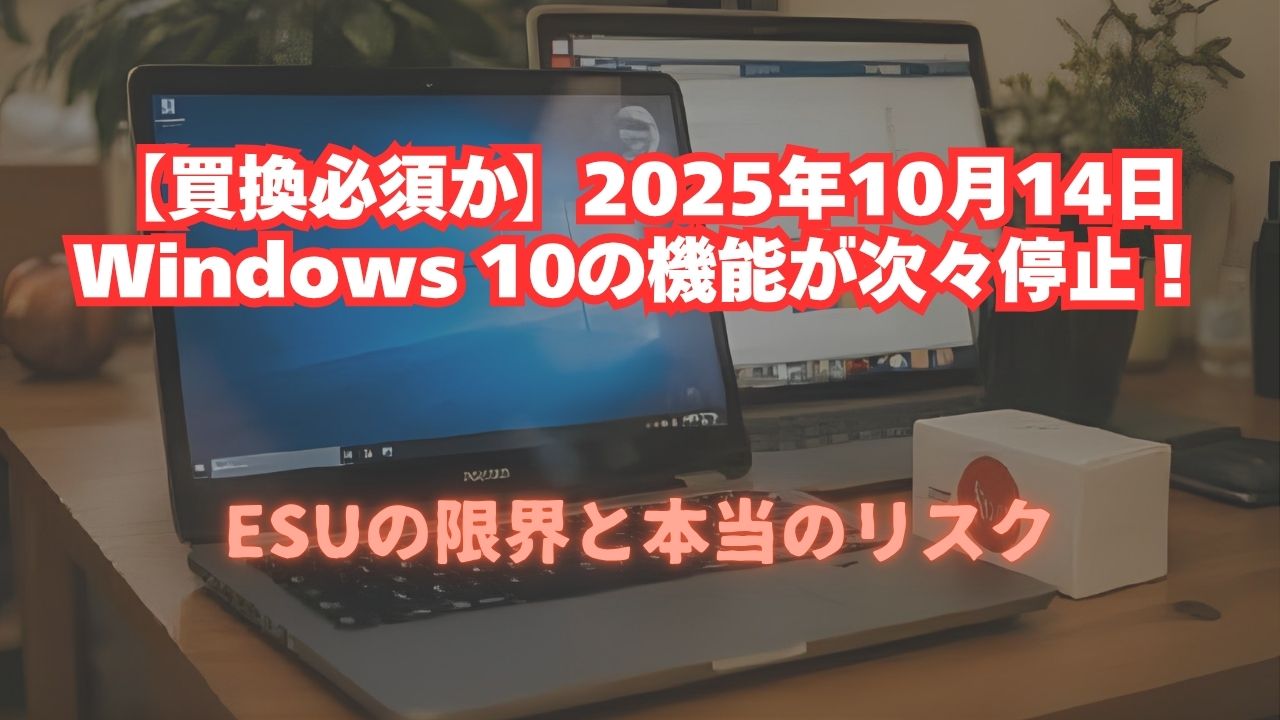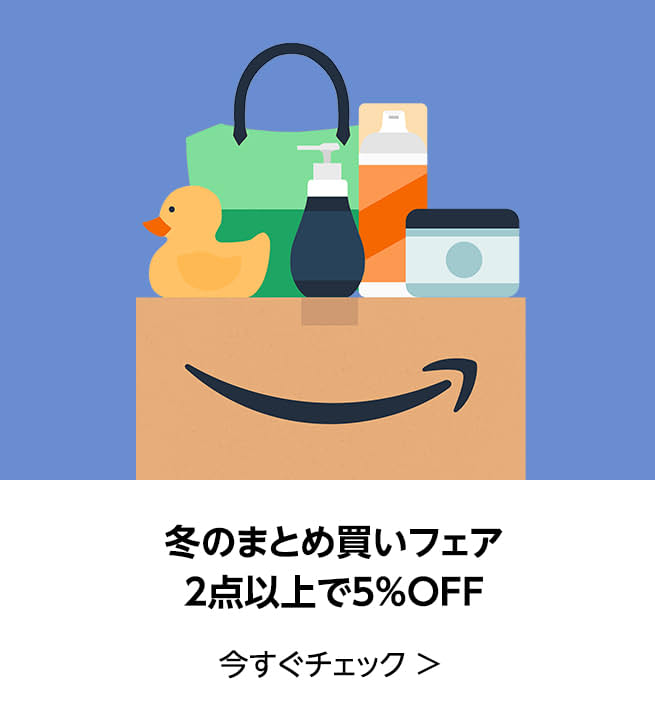2025年10月14日にWindows 10のサポートが終了することは、すでに多くの方がご存知だと思います。しかし、Microsoftが「ESU(Extended Security Updates)」を提供するということになり、一定期間のセキュリティ更新が継続されることになりました。「これで一安心」と思った人も多いと思うのですが、実はそうではありません。セキュリティは大丈夫かもしれませんが、肝心のアプリなどは次第に使えなくなってきています。
実際に金融機関や会計ソフトメーカーが続々と「Windows 10推奨環境外」への移行を発表しており、ビジネスで欠かせないOffice 2024の長期サポートもWindows 11が前提となっています。さらに、ゲーム関連機能でもすでに不具合が報告され始めています。
そこで、ESUの本当の位置づけと限界、そして個人利用で起きうる問題について詳しく解説します。Windows 10を継続利用する際のリスクを正しく理解して、適切な判断をしてもらいたいと思います。
ESUって何?本当に安心できるの?
Windows 10のサポート終了について調べていると、必ず出てくるのが「ESU」という言葉ですよね。「これがあれば安心」という情報もよく見かけますが、実際のところはどうなのでしょうか。まずはESUの正体と、その限界について詳しく見ていきましょう。
ESUの正式名称と目的
ESU(Extended Security Updates)は、Windows 10のサポート終了後に提供される「延長セキュリティ更新プログラム」です。名前の通り、あくまで「セキュリティ」に特化した限定的なサポートなんですね。
ESUについては、以下の記事で詳しく解説していますので、併せてご覧ください。
ESUで提供されるもの・されないもの
ESUがあれば「今まで通り使える」と思われがちですが、実はそうではありません。何が継続されて、何が保証されないのか、具体的に見てみましょう。
ESUで継続されるもの
まず、ESUで実際に継続されるサポートは次の通りです。
- セキュリティ更新プログラム:ウイルスやマルウェアから守るための最低限の更新
- Microsoft Defenderなどのセキュリティ機能:Windows標準のセキュリティソフトの基本機能
ESUでは保証されないもの
一方で、ESUでは次のようなサポートは提供されません。これが重要なポイントです。
- 新機能の追加:便利な新しい機能は一切追加されない
- 既存機能の維持・改善:今使えている機能も突然使えなくなる可能性がある
- 非セキュリティ関連のバグ修正:動作がおかしくても修正されない場合がある
- サードパーティソフトとの互換性:他社製ソフトとの連携は保証対象外
- 業務アプリケーションとの連携保証:OfficeやAdobe製品などとの連携も対象外
つまり、ESUは「セキュリティ更新の継続」が目的であり、Windows 10の既存機能や同梱アプリ、サードパーティ連携の「維持・改善」を保証するものではありません。特にビジネス利用では、この違いが大きな影響を与える可能性があります。
なお、ESUは個人向けは最長1年、企業向けは最長3年(年次契約)など提供形態に差があります。提供可否や価格、入手方法はエディションや契約種別によって異なるため、最新の公式情報を必ず確認してください。
また、Microsoft Defenderなどのセキュリティ機能について、保証対象はあくまでセキュリティ更新であり、個別機能全般が保証されるわけではない点は注意が必要です。
ビジネスで必須のOffice 2024、Windows 10で長期利用できる?
ビジネスで最も使用頻度が高いのは、やはりWord、Excel、PowerPointといったOfficeアプリケーションですよね。Windows 10のサポートが終了しても、Officeは問題なく使い続けられるのでしょうか。
Office 2024の長期サポート状況
Office 2024はWindows 10で使い続けられるのか?という点ですが、結論から言うと、Office 2024/LTSC 2024はWindows 10でも動作します。しかし、Windows 10のサポート終了後はWindows 10上でのサポート継続は想定されず、長期利用はWindows 11が実質前提です。
つまり、Office 2024やOffice LTSC 2024はWindows 10のサポート終了とともに、実質的に「推奨外」の扱いになります(詳細はMicrosoft公式FAQを参照)。
これはMicrosoft製品同士の話なので、ESUがあっても関係ないんですね。Word、Excel、PowerPointなどを長期的に使い続けたい場合は、Windows 11への移行が必要になります。
Microsoft 365との関係性
Microsoft 365(旧Office 365)については、少し複雑な状況になっています。
まず、2025年10月14日以降、Windows 10上のMicrosoft 365アプリは「非サポートOS上での利用」となります。しかし、アプリは動作を継続し、セキュリティ更新は2028年10月10日まで提供されます。機能更新はバージョン2608が最終となります。
機能更新の終了スケジュール
新機能の追加はバージョン2608が最後となり、次のタイミングで打ち止めになります。
- Current Channel(個人・ファミリー含む):2026年8月
- Monthly Enterprise Channel:2026年10月13日
- Semi-Annual Enterprise Channel:2027年1月12日
いずれのチャネルでも、Windows 10上での最終機能版はバージョン2608です。以降は機能追加がなく、セキュリティ更新のみが2028年10月10日まで継続される形です。
サポート対応の変更
2025年10月14日以降、Windows 10固有の問題でサポートに問い合わせをした場合、基本的にWindows 11への移行を求められます。移行できない場合は限定的なトラブルシューティング支援のみとなり、バグ報告や製品更新要求は受け付けられません。
実際にどう判断すべきか
つまり、Microsoft 365は「部分的な延長サポート」という位置づけです。セキュリティは保たれるものの、最新機能を使い続けたい場合はWindows 11への移行が必須となります。特にビジネス利用では、機能が固定されることで業務フローに影響が出る可能性もあるため、早期の移行検討がおすすめです。
実際に起きている問題:アプリケーションの不具合事例
ESUの限界について説明してきましたが、「実際にはどんな問題が起きているの?」と疑問に思われる方も多いでしょう。ここでは、現在Windows 10で実際に報告されている具体的な問題を見てみましょう。
Xboxゲームバーのクラッシュ問題
最近、Windows 10でXboxゲームバーの設定画面を開こうとするとエラーでクラッシュする問題が報告されています。この機能は単なるゲーム機能ではなく、画面録画や配信、パフォーマンス監視など、ビジネスでも活用される重要な機能なんですね。
なぜこの問題が重要なのか
Xboxゲームバーと聞くと「ゲーム機能だから関係ない」と思われるかもしれませんが、実はそうではありません。Xboxゲームバーは次のような用途で広く使われています。
- プレゼンテーション画面の録画:会議資料や操作手順の記録
- オンライン会議の録画:重要な会議内容を録画して後で確認
- ソフトウェアの操作手順動画作成:マニュアル作成や教育用コンテンツ制作
- システムパフォーマンスの監視:PCの動作状況をリアルタイムで確認
さらに問題なのは、この件に関するMicrosoftのサポート記事が見当たらない(撤収が指摘されている)という報告もあることです。現時点で公式に方針が明言されたわけではありませんが、Windows 10で設定画面がクラッシュする複数の報告があり、関連サポート記事撤収の指摘も見られます。このような状況から、機能の安定性に関する懸念が高まっている状況です。
今後予想されるアプリケーション全般の問題
Xboxゲームバーの問題は氷山の一角に過ぎません。今後もさまざまなアプリケーションで同様の問題が発生する可能性があります。考えられるアプリや機能ごとの懸念点を整理します。
ただし、次にまとめたものは一般的な傾向・可能性であり、各サービスの対応はベンダーの公式告知に依存します。最新のサポート情報をご確認ください。
- DirectX関連の最適化停止
新しいゲームタイトルや配信ソフトで使用されるDirectXの最適化が、Windows 10では停止される可能性があります。 - ゲーム配信・録画機能の制限
OBS StudioやXSplitなどの配信ソフトとの連携機能が、順次Windows 10では利用できなくなる可能性があります。 - VRコンテンツ対応の終了
Windows Mixed RealityやSteamVRなどのVR関連機能は、新しいヘッドセットやアプリケーションでWindows 10サポートが打ち切られる可能性が高いです。 - 配信・動画制作系アプリの機能制限
DaVinci Resolve、Adobe Premiere Proなどの動画編集ソフトや、CanvaやFigmaなどのデザインツールでも、新機能や高度な機能から順次Windows 10対象外となる可能性があります。 - コミュニケーション系アプリの制限
Discord、Slackなどのコミュニケーションツールでも、画面共有やボイスチャットの高度な機能、AI機能などが段階的に制限される可能性があります。 - 開発・技術系ツールの対応終了
Visual Studio Code、Docker、各種IDEなど、開発者向けツールは特に新しいOSへの対応を重視する傾向があり、Windows 10サポートの終了が早い可能性があります。 - 一般ユーザー向けアプリの機能縮小
Spotify、Netflixなどのエンターテイメントアプリのデスクトップ版や、各種ブラウザの新機能、クラウドストレージの同期機能なども、段階的に制限される可能性があります。
金融・証券サービスでの深刻な影響
Windows 10のサポート終了が最も深刻な影響を与えるのが、金融・証券サービスの分野です。お金に関わるサービスだけに、セキュリティ要件が厳しく、対応も早いのが特徴ですね。
SBI証券の対応が示す業界動向
SBI証券では、2025年10月14日のWindows 10サポート終了に合わせて、同社のWebサイトや取引ツールでWindows 10を推奨環境から外すことを告知しています。
これは単なる形式的な変更ではありません。推奨環境外のOSでトラブルが発生した場合、取引時のシステムエラーでサポートが受けられない可能性や、重要な取引タイミングでのシステム障害リスクが高まる可能性があります。
その他金融機関への波及
他社でも同様の告知が増えています。ご利用中サービスの推奨環境ページを定期的に確認してください。資産運用や日常的な銀行取引に支障をきたす可能性があります。
Windows 10を使い続けるとどんなことが起こるのか?
各金融サービスがWindows 10を推奨環境から外した後に、Windows 10を継続利用した場合、次のような問題が発生する可能性があります。つまり、このような状況でWindows 10を使い続けることは、実務上のリスクが高まる可能性があります。
取引時のトラブル対応
- システムエラーが発生しても「推奨環境外のため対応できません」と言われる可能性
- 重要な取引タイミングでシステムが不安定になっても自己責任となるリスク
- 取引ツールが突然使用できなくなっても保証されない
セキュリティ関連の問題
- 不正アクセスやセキュリティ事故が発生した際の責任所在が不明確になる
- 二段階認証などの新しいセキュリティ機能が利用できない可能性
- 保険や補償の対象外となる可能性
日常的な利用制限
- ログインできない、画面が正常に表示されない可能性
- 入出金や振込などの基本機能が利用できなくなる
- スマートフォンアプリとの連携機能が使えなくなる
業務ソフトウェアのサポート終了が加速
金融サービスだけでなく、日常業務で使用するソフトウェアでもWindows 10のサポート終了が相次いで発表されています。特に法制度に関わるソフトウェアでは、対応が早く進んでいます。
例えば、JDL(会計系ソフト)では、Windows 10のサポート終了に伴い、同社ソフトのWindows 10サポートを終了することを案内しています。
会計・税務ソフトは法制度の変更に対応する必要があるため、サポート外のOSでの利用は電子申告(e-Tax)との連携不具合や、法改正に伴うアップデート適用不可などの問題を引き起こします。そのため、他の業務系ソフトウェアのサポート終了は加速しそうです。
リモートワーク・テレワークへの影響
在宅勤務が定着した現在、リモートワークに必要なツールが使えなくなることは大きな問題ですよね。Windows 10のサポート終了は、こうしたテレワーク環境にも影響を与える可能性があります。
- Web会議システムとの互換性
将来的な傾向として、Zoom、Microsoft Teams、Google Meetなどの会議システムも、要件引き上げやAI機能などの新機能がWindows 11優先となる可能性があります。特に画面共有、録画、セキュリティ機能から順次対象外となるリスクがあります。
- クラウドサービスの認証問題
多要素認証やシングルサインオン(SSO)機能は、OSレベルのセキュリティ機能と連携しています。Windows 10のサポート終了により、これらの認証機能に制限が生じる可能性があります。
個人事業主・フリーランスが知っておくべきリスク
個人事業主やフリーランスの方は、会社のIT部門のサポートがない分、自分で判断して対応する必要がありますよね。Windows 10のサポート終了は、特に以下のような業務に大きな影響を与える可能性があります。
- 確定申告への影響
国税庁のe-Taxシステムは、推奨環境外のOSでのサポートを段階的に終了する傾向があります。確定申告時期に突然利用できなくなるリスクを避けるためにも、早期の対応が必要です。 - クライアントとのファイル共有
Word、Excel、PowerPointファイルの互換性や、PDF作成機能に問題が生じる可能性があります。クライアントとの重要なやり取りで支障をきたすリスクがあります。 - 電子署名・電子契約サービス
DocuSign、Adobe Sign、クラウドサインなどの電子契約サービスは、OSのセキュリティ機能に依存しています。契約業務に支障をきたす可能性があります。
エンターテイメント・クリエイティブ分野での影響
ゲームや動画制作、配信活動を楽しまれている方にとっても、Windows 10のサポート終了は無視できない問題です。クリエイティブ系のソフトウェアは新機能の追加が頻繁で、OS要件も厳しくなる傾向があります。
NVIDIAはWindows 10のドライバサポートを延長
明るいニュースもあります。NVIDIAはWindows 10向けドライバのサポート継続を公式に表明しており、少なくとも2026年頃までのサポート(セキュリティ更新を含む)延長がアナウンスされています。
ただし、サポートの内容には違いがあります。
継続されるサポート
- セキュリティ更新・致命的不具合修正
- 基本的なドライバ機能
- 現在のGPU性能の維持
制限される可能性があるもの
- 新機能や最適化(Windows 11優先)
- 最新のGPU機能(RTX Video、NVENC最適化、AIアップスケーリング、G-SYNC関連の拡張など)
- 新しいゲームタイトルでの最適化
結論として、現有環境の延命はしやすくなる一方、最新機能は追いづらくなります。つまり、Windows 10向けドライバの継続提供は「互換・安定性の維持」が主眼であり、「最新機能の先行提供や最適化の厚さ」はWindows 11優先になりやすい可能性があります。
そのため、配信・編集・最新ゲームの最高パフォーマンスを狙う場合はWindows 11移行が無難です。
動画配信・編集ソフトの対応
OBS Studio、Streamlabsなどの配信ソフトは、Windows 10での新機能サポートを段階的に終了する可能性があります。ライブ配信やYouTube投稿を行っている方は注意が必要です。
Adobe Creative Suiteとの互換性
PhotoshopやPremiere Proなどのクリエイティブソフトも、長期的にはWindows 10サポートを縮小する可能性があります。特に新しいAI機能や高度なエフェクトから順次対象外となる可能性が高いです。
ゲーム開発・配信環境
Unity、Unreal Engine、Blenderなどの開発ツールでも、最新の機能やプラグインがWindows 10では利用できなくなるリスクがあります。
法人向けの対応ポイント
法人の場合は、次の点を重点的に確認してください。
最優先チェック項目
会計・給与計算ソフトのサポート状況
税制改正や社会保険制度の変更に対応するため、法制度との整合性が必須です。サポート対象外になると法的リスクや申告不備の可能性があります。
VPNクライアントの対応方針
企業ネットワークへの安全な接続が困難になると、リモートワーク自体が不可能になります。セキュリティ要件が厳しいため早期に対象外となる可能性が高いです
業務必須アプリケーションの動作保証
CRM、ERP、電子契約システムなど、業務の根幹を支えるシステムが使用できなくなると事業継続に直接影響します
対応戦略
経理・財務部門のPCを最優先で移行
会計処理や税務申告、資金管理など、事業の根幹業務が停止すると企業運営に致命的な影響を与えます。法的義務のある業務でもあるため、最優先での対応が必要です
段階的な買い替え計画の策定
全PCを一度に買い替えるのは資金負担が大きいため、業務への影響度と予算を考慮した優先順位を設定し、計画的に移行を進めることが重要です
ESUは「時間稼ぎ」として位置づけ、本格移行の準備期間とする
ESUに依存した長期運用は危険です。移行計画の検討、予算確保、システム選定などの準備期間として活用し、確実にWindows 11への移行を完了させる必要があります
詳細な法人向け対策については、システム管理者やIT部門との綿密に相談して進めたほうがいいでしょう。
よくある誤解
「ESUがあるから安心」と考えている人が誤解している点についてまとめました。
Q: ESUを購入すれば、業務アプリも安心して使えるよね?
A: いいえ。ESUはWindows自体のセキュリティ更新のみで、業務アプリケーションのサポートとは別問題です。各ソフトメーカーが個別にサポート終了を決定する可能性があります。
Q: Office 2024は長期間Windows 10で使えるよね?
A: 長期利用は困難です。Microsoft製品であってもWindows 10での長期サポートは想定されていません。Office利用を継続するには、Windows 11への移行が現実的です。
Q: ゲームや配信には影響ないよね?
A: 影響が生じる可能性が高いです。すでにXboxゲームバーで問題が発生しており、今後も配信ソフトやゲーム関連機能で順次サポート終了が予想されます。
Q: リモートワークには影響ないよね?
A: 影響が生じる可能性が高いです。Web会議、クラウドサービス、VPNなど、リモートワークに必須のツールが段階的に利用困難になる可能性があります。
まとめ:総合的な判断が必要
ESUは確かにWindows 10の延命手段として提供されますが、個人利用においても「時間を稼ぐ」ための最後の選択肢に過ぎません。Office 2024、会計ソフト、金融サービス、ゲーム・配信環境など、日常的に使用するアプリケーションやサービスの多くが、Windows 10での長期利用を想定していないのが現実です。
特に次の用途でPCを使用している方は、早急な対応が必要です。
- ビジネス用途: Office、会計ソフト、オンラインバンキング、Web会議
- クリエイティブ用途: 動画編集、画像処理、配信、ゲーム開発
- エンターテイメント: ゲーム、動画配信、VRコンテンツ
肝心の対応策ですが、最もリスクが低いのは、可能な限り早期にWindows 11へ移行することです。公式にはTPM 2.0や第8世代Intel CPU以降などの要件がありますが、最近の報告では、これらの要件を満たさないPCでもWindows 11 24H2のクリーンインストールが可能になっているケースがあります。
ただし、この現象は以下の点に注意が必要です。
- 公式サポート対象外のため、問題が発生してもMicrosoftからのサポートは受けられない
- セキュリティ機能の一部が正常に動作しない可能性がある
- 将来のアップデートで再び制限が強化される可能性がある
- アップグレード(既存環境からの更新)では従来通り制限がある
要件を満たさないPCをお使いの場合は、クリーンインストールという選択肢もありますが、リスクを理解した上での自己責任となります。メインPCとして長期利用する場合は、公式要件を満たすPCへの買い替えを検討したほうがいいでしょう。なお、要件を満たさないPCへのインストールについては、以下の記事で詳しく解説しています。
いずれにせよ、Windows 10が問題なく使い続けられるというのは誤解です。延命に伴うリスクを正しく理解して、ご自身の利用状況に応じた適切な判断をしていただければと思います。
(雑感)
にしても、ちょっとゴタゴタしていますね。長らく使われてきたWindows 10のサポート終了ですから仕方ない部分もありますが、Microsoftの舵取りも色々と不手際が多いような気がしています。ゲームバーのクラッシュについても、意図的かどうかはわかりませんが、疑問を投げかけられても仕方がないような気がします。最近のMicrosoftにはあまりいい印象がないので、余計にそう感じてしまうのかもしれません。