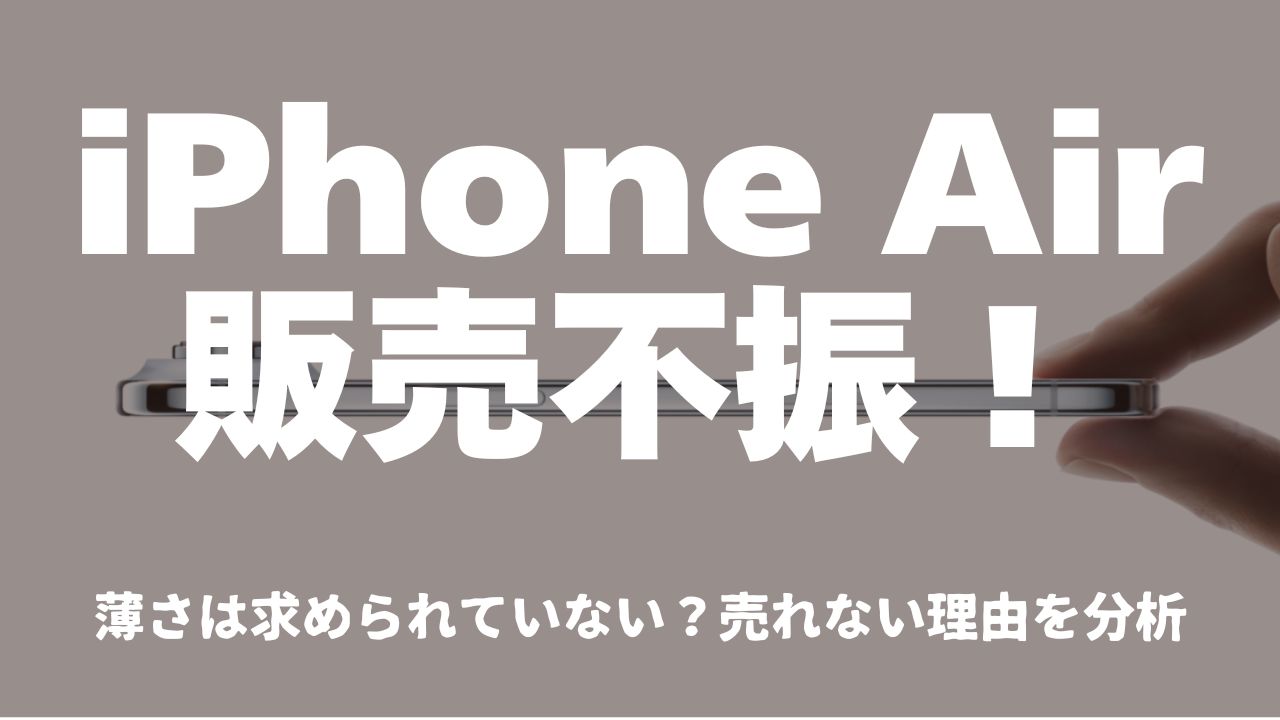わずか5.5mmの超薄型ボディで注目を集めたiPhone Airが、発売直後から世界各国で売れ残る異例の事態に。同じiPhone 17シリーズの他モデルは好調なのに、なぜAirだけが苦戦しています。かつてのiPhone miniの失敗とも重なるこの現象から、薄型・小型スマホが抱える根本的な課題が見えてきました。
「iPhone Air」売上不振の衝撃─期待の新モデルに何が起きたのか
Appleの新作「iPhone Air」が、予想外の販売不振に陥っています。2025年9月の発売直後から世界各国で在庫が余る事態となり、生産縮小が報道される異例の展開になりました。同じiPhone 17シリーズのProやPro Maxは軒並み納期が遅れるほどの人気ぶりなのに、Airだけが売れ残っている状況は何とも対照的ですよね。
発売開始から数時間後の各国Apple公式サイトを調べたデータによれば、アメリカ、カナダ、イギリス、フランス、韓国、シンガポールなど多くの国でiPhone Airだけが発売日到着可能な在庫状態でした。他のモデルがすべて納期遅れになっている中、Airだけが余っているという状況は、消費者の関心の薄さを如実に物語っています。
この不人気ぶりを受けて、Appleは早々に生産調整に乗り出しました。Morgan Stanleyのアナリストによれば、iPhone 17シリーズ全体の生産台数は当初予定の8,400万〜8,600万台から9,000万台超へと引き上げられたものの、その増産分はすべてProモデルと標準モデルに向けられ、Airの生産は逆に削減される見込みとのこと。
期待の新製品がなぜここまで苦戦しているのか。その背景には、スマートフォン市場における根深い構造的問題がありそうです。
iPhone Airが不人気な理由─薄さと引き換えに失ったもの
iPhone Airの最大の売りは、わずか5.5mmという驚異的な薄さでした。しかし、この超薄型デザインを実現するために、多くの妥協を強いられたのは事実。そしてその妥協こそが、一般ユーザーの購買意欲を削いだ最大の要因となっています。
まず挙げられるのがカメラの制約。iPhone Airは薄さを優先した結果、シングルカメラ構成となりました。今や複数のカメラレンズは当たり前の時代において、シングルカメラはあまりにも物足りない。実際、同時期に発売されたSamsungのGalaxy S25 Edgeが薄型ボディでありながらデュアルカメラを搭載しており、SNSや海外メディアでは「完成度が低い」との評価が広がってしまいました。
次にバッテリー容量の削減も大きな問題です。薄型化のため3,100mAhというバッテリー容量は、他のiPhone 17モデルと比較してもかなり小さめ。スマホを使う人にとってバッテリーの持ちは死活問題ですからね。「薄さよりも一日中安心して使える方がいい」というのが、多くのユーザーの本音です。
さらに価格設定もミスマッチ。iPhone 17は12万9,800円からなのに対し、iPhone Airは15万9,800円からと3万円も価格差がある。しかも機能的には劣っており、堅牢なバッテリーとプロレベルのディスプレイを備えているiPhone 17に対し、Airのアドバンテージは「見た目の薄さ」という部分だけです。つまり、ユーザーは薄さというロマンよりも実用性を重視しているということですね。スマホは普段使いするものですから、当たり前と言えば当たり前の話です。
このような結果、iPhone Airは「中途半端なポジション」になってしまいました。標準モデルほどコスパが良くなく、Proモデルほど高機能でもない。この「どっちつかず」の立ち位置が、消費者の選択肢から外されてしまう結果を招いたといえるでしょう。
miniシリーズの失敗と重なる構図─ニッチ層への訴求という落とし穴
iPhone Airの苦戦を見ていると、どうしても思い出すのがiPhoneのminiシリーズです。2020年に登場したminiシリーズは、5.4インチというコンパクトサイズで「小さなスマホを求める層」に向けて投入されましたが、結果として市場から姿を消すこととなりました。
miniとAirには、驚くほど共通点があります。それは「特定のニッチ層には熱狂的に支持されるが、マス市場では受け入れられない」という構造。いわゆる「刺さる人には刺さる」というやつですね。
では、一般ユーザーは実際にスマホを選ぶとき、何を最も重視しているのか?各種調査やアンケート結果を見ると、その答えは明確です。
- 画面サイズとディスプレイ品質:動画視聴・SNS閲覧・ゲームなど、スマホには大きく美しい画面は必須条件
- バッテリー持続時間:一日中充電なしで使えることは、多くのユーザーにとって譲れない要素
- カメラ性能:SNS投稿やビデオ通話が日常化した現代では、カメラの性能は「あったら嬉しい」ではなく「なくては困る」機能
- 処理性能とメモリ:複数アプリの同時使用やゲームプレイをスムーズにこなせるスペックが必要
- 価格とコストパフォーマンス:高性能化が進む中、価格が手頃であることも依然として重要な要素
一方で、「薄さ」や「コンパクトさ」といった要素は、上位に入ることはほとんどありません。もちろん「ポケットに入りやすい」「片手で持ちやすい」といったメリットはあるけれど、それが他の実用的機能を犠牲にしてまで追求すべき価値とは見なされていないのが実情。
正直、iPhone Airだけ見れば、ここに挙げた項目のスペックは満たしていると思います。しかし、標準モデルと比較すると劣って見えるのは事実。
iPhone 17シリーズの中で標準モデルとProモデルが好調な理由も、まさにここにあります。標準モデルは必要十分な機能を提供し、Proモデルは最高峰の性能とカメラを備える。どちらも「実際の使い勝手」に直結する価値を提供している。だからこそ、ユーザーは納得して購入するわけですね。
薄型・小型スマホが市場で生き残るには?
iPhone AirとiPhone miniの失敗は、決して偶然ではありません。これらは「薄型・小型スマホが市場の主流になり得ない」という構造的な現実を浮き彫りにしています。
とはいえ、iPhone Airの存在意義がまったくないわけではありません。一部のアナリストは、「Airはニッチ市場を開拓する長期戦略の一環」と見ています。MacBook Airも当初は懐疑的な目で見られましたが、時間をかけて市場に受け入れられ、今ではAppleのノートPC部門の主力製品となっています。iPhone Airも同様に、将来的には折りたたみスマホなど次世代デバイスへの技術的な足がかりとなる可能性はあるはずです(あると思いたい)。
まとめ:「ロマン」と「現実」の狭間で
iPhone Airの売上不振は、「薄型・小型スマホ」が抱える本質的な課題を浮き彫りにしました。ガジェット好きにとっては魅力的な「ロマン」であっても、一般ユーザーにとっては購買動機にならない。iPhone miniの失敗を再び繰り返されてしまっています。
現代のスマートフォン市場では、実用性こそが最優先されます。バッテリーが長持ちし、カメラが高性能で、画面が見やすく、価格も納得できる。こうした「当たり前」をしっかり満たすモデルこそが、結局は市場で生き残っていくのでしょう。
もちろん、挑戦的なデザインや技術革新が無意味だというわけではありません。ですが、「見た目の美しさ」や「技術的なロマン」だけでは、今の消費者の心は動かせない。それが現実なのかもしれないですね。