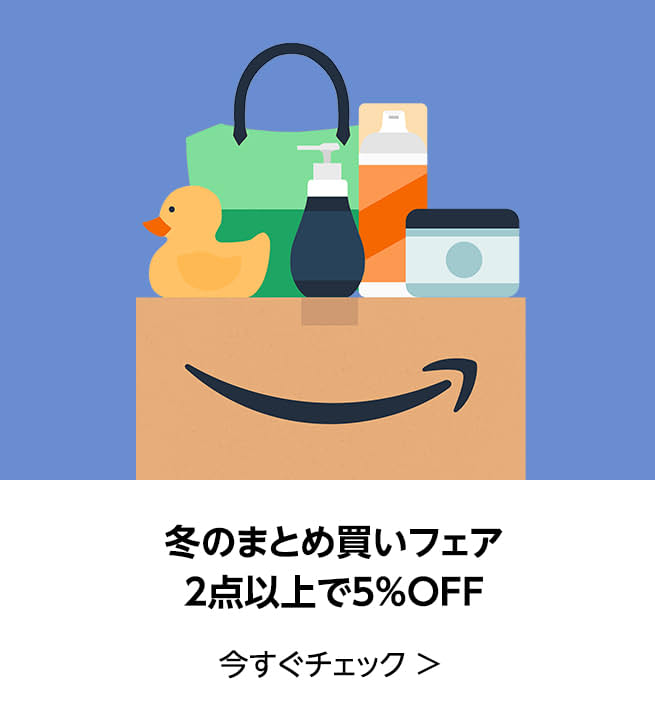最近、家電量販店やネットショップでよく見かけるようになった「ARM版Windows PC」。バッテリーが長持ちして、価格も手頃で魅力的に見えますよね。でも、ちょっと待ってください。その「安さ」に飛びつく前に、知っておくべき重要な落とし穴があるんです。
そこで、ARM版Windows PCの現実を徹底解説します。メリットだけでなく、メーカーが積極的にアナウンスしていないデメリットも含めて、購入前に絶対知っておきたい情報をお伝えします。
そもそもARM版とx86版って何が違うの?
まず、基本的な違いから理解しておきましょう。
CPU(プロセッサー)の設計思想が根本的に違う
従来のWindows PCは、CPUにIntel Core i5/i7やAMD Ryzenなどを搭載しています。これをx86/x64版と呼びます。これらのCPUは30年以上の歴史があり、現在流通しているほぼすべてのWindowsソフトがこの形式で作られています。高性能ですが、消費電力が大きく発熱も多いのが特徴です。一般的なWindows PCはこちらのタイプですね。
一方、昨年から登場してきているのがARM版と呼ばれるWindows PCです。こちらは、Qualcomm Snapdragon X EliteやX PlusなどのCPUを搭載しています。これらのCPUはスマートフォンと同じ系統の省電力設計となっています。従来のWindowsソフトは「エミュレーション」という変換技術で動かす仕組みになっています。
簡単に言うと、ARM版は「スマホのCPUを高性能にしてパソコンに載せた」ようなイメージです。
購入前に確認!ARM版かどうかの見分け方
店頭やネットショップでARM版かどうかを見分ける最も確実な方法は、CPU名を確認することです。「Snapdragon X Elite」や「Snapdragon X Plus」と書かれていればARM版で、「Intel Core i3/i5/i7」や「AMD Ryzen 3/5/7」なら従来版です。

ARM版のほとんどはCopilot+ PCとして販売されている
ARM版のほとんどは、最近話題の「Copilot+ PC」として販売されています。つまり、Copilot+ PCの購入を検討する場合は、ARM版かx86版のいずれかを選択する形になります。
確認する方法ですが、前述の通りに必ずCPUの種類を確認してください。なお、「Windows 11 on ARM」の表記があれば確実にARM版ですし、「長時間バッテリー駆動」を強くアピールしているモデルはARM版の可能性が高いですが、最終的にはCPU名で判断するのが確実ですね。
機種名でも判断できることがあります。Surface Pro(ARM版)やSurface Laptop(ARM版)は2024年後半以降のSnapdragon搭載モデルが該当しますし、各社の薄型軽量モデルで「○○ Snapdragon Edition」などの名称が付いているものもARM版です。
もしわからなければ店員さんに「これはARM版ですか?」と直接聞いてみてください。
ARM版Windows PCのメリット
まずは、ARM版Windows PCのメリットについて確認していきましょう。
バッテリー持ちが圧倒的に良い
従来のIntel製CPUを搭載したノートPCと比べて、ARM版は圧倒的にバッテリーが長持ちします。MacBook Airに匹敵する、10時間以上の駆動時間を実現しているモデルも珍しくありません。
外出先での作業が多い方にとって、これは大きなメリットですよね。
価格が抑えられている
ARM系のCPU(Snapdragon X Eliteなど)は製造コストが比較的安く、本体価格も手頃に設定されていることが多いです。ほぼ同じぐらいのスペックを持つIntel搭載モデルより数万円安い場合もあります。
発熱が少なくて静か
省電力設計のおかげで発熱が少なく、ファンが回りにくい、またはファンレス設計になっているモデルもあります。図書館やカフェでの作業でも、周りを気にせず使えるのは嬉しいポイントです。
AI機能が充実
最新のSnapdragon X系CPUには専用のAI処理ユニットが搭載されており、WindowsのAI機能(リコール、小クリエイター、ライブキャプション、クリックして実行など)などのローカルAI機能が動作します。これからの時代を先取りしている感じがしますよね。
ここからが本題。ARM版の「思わぬ落とし穴」とは?
魅力的に見えるARM版Windows PCですが、実は大きな落とし穴があります。それが「互換性問題」です。
「Windowsなのに動かない」アプリが存在する
これが最も深刻な問題です。ARM版Windows PCは、従来のx86/x64向けに作られたアプリを「エミュレーション」という技術で動かします。でも、この仕組みには限界があるんです。具体的には、正常に動作しないアプリが、結構な数あるという点です。
クリエイティブ系で動作しないアプリ
まず、クリエイティブ系では、Adobe Creative Cloudの多くのアプリが要注意です。Adobe CCのアプリの中では、PhotoshopのみARMに対応しています。しかし、その他のアプリ(IllustratorやPremiere Pro、After Effects、InDesignなど)はエミュレーションでの動作となり、不安定になったりパフォーマンスが落ちたりすることがあります。
これ以外にも、動画編集ソフトや3Dソフトの多くはまだARM版に最適化していないものが多く、エミュレーション動作によるパフォーマンスや機能制限があります。
ビジネス系で動作しないアプリ
日本語入力にこだわりがある方も注意が必要です。ATOKは公式に動作保証外となっており、Google日本語入力も正常動作の保証がありません。大学や研究機関でよく使われるSPSSやJMPなどの統計解析ソフトも、ARM版での提供はされていない状況です。
また、電子申請系や会計ソフト、e-Tax関連など業務・法人向けソフトも、多くがx86依存で動作未検証の状況が続いています。
拡張機能が動作しないこともある
意外な落とし穴として、Microsoft Officeの拡張機能(アドイン)も要注意です。Office本体は動作しますが、業務でよく使われる各種アドインや、プラグイン系のソフトウェアの多くがx86依存で作られているため、ARM版では正常に動作しない場合があります。「Officeが使えるから大丈夫」と思っていても、実際に仕事で必要な機能が使えないという事態になりかねません。
ゲーム系で動作しないアプリ
ゲーム好きの方には厳しい現実があります。ValorantやLeague of Legends、Apex Legends、Call of Dutyなど人気タイトルの多くが、アンチチート機能やOpenGLの制約で動作しません。
また、グラフィックスAPIや最適化がx86/x64前提で作られているゲームでは、ARM版で動作テストが十分に行われていないことがほとんどです。そのため、アプリはパフォーマンスが安定しないことが少なくありません。
周辺機器も要注意
ソフトだけでなく、周辺機器との互換性も問題になることがあります。特に注意したいのがプリンターや複合機で、メーカー純正ドライバがx86版しか提供されていないケースが多数あります。スキャナーについても専用ソフトが動作保証外となっていることが多く、ペンタブレットではWacomなどの一部製品で制限が発生する場合があります。
特に、少し古めのプリンターをお使いの方や、業務用の特殊な機器を使用される方は事前の確認が必須。ただ、古いデバイスや特殊なデバイスはかなり厳しいというのが実情でしょう。
Amazonの口コミなどを見ても、互換性で困っている人のレビューが散見できます。

メーカーは積極的にデメリットを宣伝していない
さらに問題なのは、MicrosoftやPCメーカーは、ARM版の問題点を積極的にアナウンスしていません。
表に出るのはメリットばかり
公式サイトや広告では「省電力」「長時間バッテリー」「AI機能」などの魅力的な面ばかりが強調されています。一方で、互換性の問題については公式FAQや技術資料の片隅に小さく書かれている程度に留まっているのが現状です。
詳しい注意喚起は第三者から
実際の互換性問題については、大学や企業の注意喚起ページ、IT系ニュース、経験者のブログなどで情報収集する必要があります。例えば、中央大学や横浜市立大学などの教育機関では、学生に対してARM版Windows PCの購入を控えるよう注意喚起を出しているんです。でも、一般の方がこういう情報に触れる機会は少ないですよね。
つまり、自分で積極的に調べない限り、こういうデメリットに気づきにくいということになります。店頭で買う場合は、店員さんに確認すれば教えてくれると思いますが、ネットショッピングの場合はそうもいきません。
「私には関係ないかも」と思った方、本当に大丈夫?
「私はネットとOfficeしか使わないから大丈夫」と思われる方もいるかもしれません。でも、実際には思わぬ場面で困ることが多いのが現実です。
「ライトユーザー」でも安心できない理由
会社や学校から特定のソフトを使うよう指示される場合があります。役所の電子申請で特定のアプリが必要になることもありますし、家族や友人から「このファイルを開いて」と頼まれることもあるでしょう。また、急にプリンターやスキャナーを使う必要が出てくることもありますよね。
こういった「想定外」の場面で、「あれ?動かない…」となるリスクが高いのがARM版の現実なんです。
互換性問題を解決できる人は限られる
もしトラブルが発生した場合、自分で調べて解決できるITリテラシーが求められます。「パソコンは使えるけど、トラブル対応は苦手」という方には向いていません。エラーメッセージを検索したり、代替ソフトを探したり、設定を変更したりといった作業が必要になる可能性があるからです。
また、互換性トラブルに直面した場合、PCメーカーや販売店によっては従来機(x86/x64)ほどの詳細サポートが受けられないこともあります。どうしても購入する場合は、公式サポート窓口の内容も事前確認したいですね。
それでも購入を検討する場合のチェックポイント
ARM版Windows PCに興味があるなら、次の点を必ず確認してください。
購入前の必須チェック事項
使用予定のソフトウェアについては、現在使っているアプリがすべてARM対応かどうかを確認することが最重要です。将来使う可能性があるソフトも調査しておきましょう。学校や職場指定のソフトがある場合は特に注意が必要ですね。
周辺機器の対応状況も忘れずにチェックしてください。プリンターやスキャナーのドライバー対応、Webカメラやマイクなどの動作確認、外付けハードディスクやUSB機器の互換性なども確認しておきたいポイントです。
サポート体制についても事前に調べておくことをおすすめします。購入店やメーカーのサポート対応範囲がどこまでなのか、互換性問題が発生した際にどのような対処法があるのかを把握しておけば安心です。
購入を避けた方が良い人
メインPCとして使用予定の方、業務用PCを探している方、家族共用のPCを検討している方は、現時点では従来のx86/x64 Windows PCを選んだ方が安全です。また、パソコンに詳しくない方やトラブル時の自己解決が苦手な方も、ARM版は避けておいた方が無難でしょう。
購入しても良いかもしれない人
逆に、サブマシンとしての用途で検討している方、新しい技術に興味があり実験的に使いたい方なら検討の余地があります。トラブル時に自分で調べて解決できる方や、使用用途が完全に確定しており、すべて動作確認済みの方であれば、ARM版のメリットを享受できる可能性が高いです。
「安さ」だけで選ぶのは危険
ARM版Windows PCは確かに魅力的な面もありますが、現時点では万人におすすめできる製品ではありません。
特に「安いから」という理由だけで購入を決めるのは危険です。大切なお金と時間を失わないためにも、しっかりと事前調査を行ってから判断することが大切ですね。
余談:Windows RTの失敗から学ぶこと
実は、MicrosoftがARM版Windowsに挑戦するのは今回が初めてではありません。2012年に「Windows RT」という製品が発売されたことをご存知でしょうか。
Windows RTは見た目は普通のWindowsでしたが、従来のWindowsソフトが一切動かず、Windowsストアアプリしか使えませんでした。当時はストアアプリの数も少なく、ユーザーは「Windowsなのに何もできない」と大きく失望しました。結果的に、Windows RTは市場から姿を消すことになったんです。
現在のARM版Windows PCは、Windows RTの反省を活かしてエミュレーション機能を搭載し、従来のソフトも動くように改良されています。しかし、完全ではない互換性という根本的な課題は依然として残っているのが現状です。
「Windows RTの二の舞にならないか?」という懸念を持つ人がいるのは、こうした歴史的背景があるからなんですね。私もこの点はかなり危惧しているというか、正直なところ、二の舞になりそうな感じがしています。
今後の展望
今後の展望ですが、ARM版Windows PCのエコシステムは徐々に改善されており、対応アプリも増えてきています。ただし、完全に安心して使えるレベルに達するまでは、まだまだ時間がかかりそうです。
そもそも、Windowsの魅力は過去の豊富な資産が使えるという点にあります。Macの場合、過去の資産を切り捨てて新しいものに移行するという文化があったので、現在のMシリーズへスムーズに移行できましたが、Windowsの場合は事情が異なります。
ですので、ARM版Windowsが軌道に乗るとしても、かなりの時間がかかると思います。
まとめ
ARM版Windows PCは革新的な技術ですし、製品自体のクオリティは決して悪くないと思います。しかし、Windows最大のメリットである互換性は確保できていません。その点を無視して、メーカーはデメリットを積極的に宣伝していないのが現状です。
そのため、ライトユーザーでも思わぬトラブルに遭遇する可能性があるため、購入前の徹底的な調査が必須です。自分の用途や技術レベルを考慮して、後悔のないパソコン選びをしてほしいと思います。
参考リンク