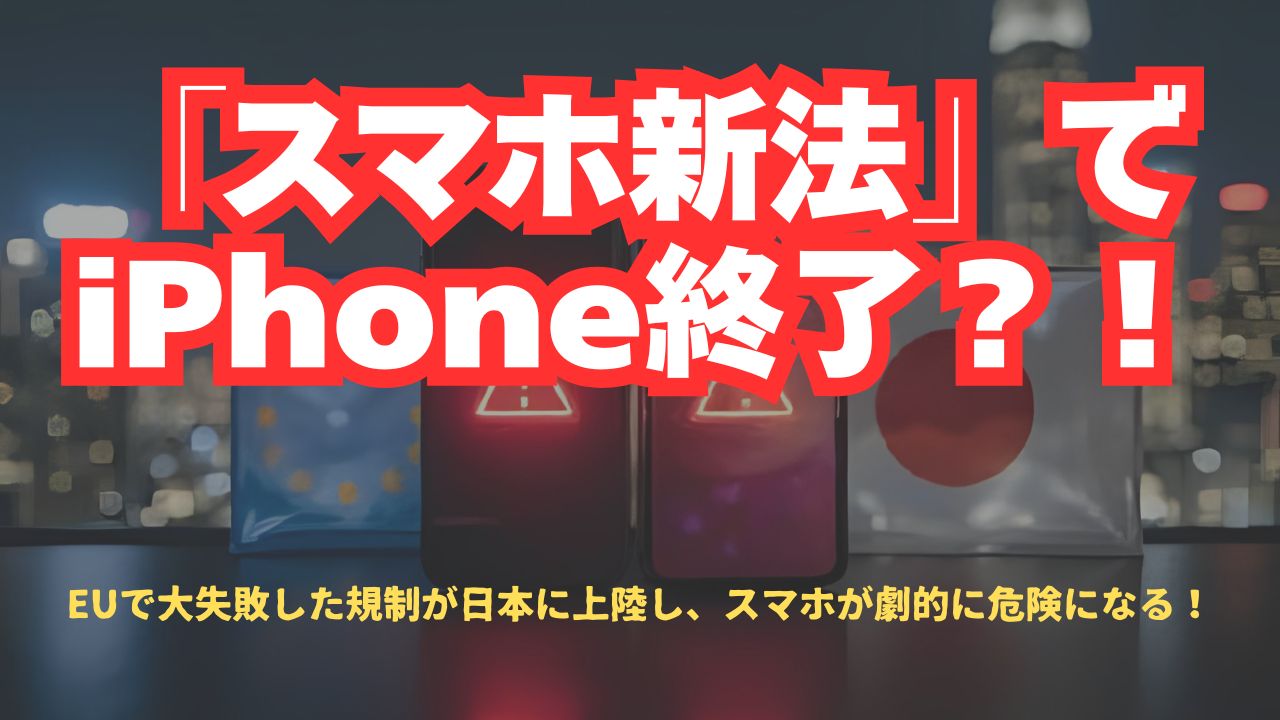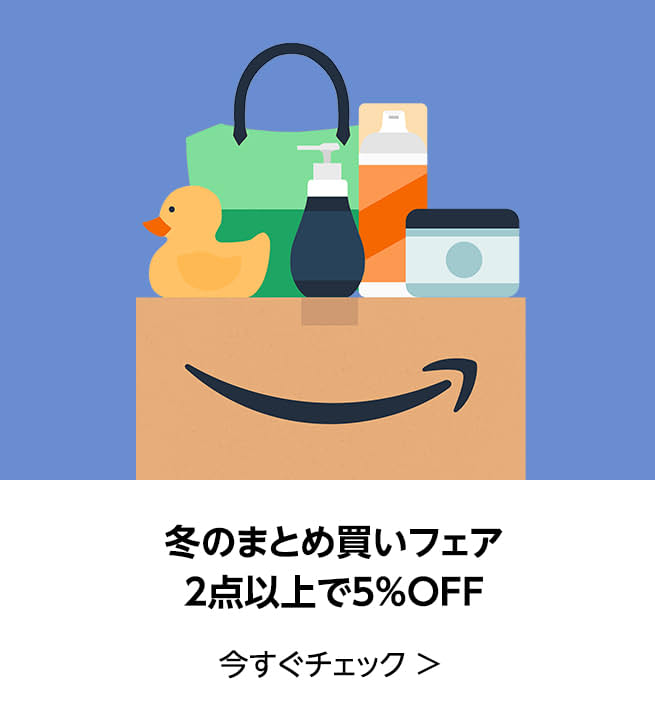みなさん、「スマホ新法」って聞いたことありますか?正式名称は「スマートフォンソフトウェア競争促進法」という長い名前の法律なんですが、2025年12月に施行される予定です。
「競争促進って聞こえはいいじゃん」と思うかもしれませんが、実はこの法律、iPhoneやAndroidスマホがとにかく不便で危険になるだけの非常に危険なものになる可能性が高いんです。はっきり言って、この法律に対しては声を上げないととんでもなく不便になるのは間違いありません。そこで、この法律がもたらす本当の影響について、わかりやすく解説していきます。
スマホ新法って何?簡単に言うと…
この法律を一言で表すと、「AppleやGoogleに『もっと自由にしろ』と強制する法律」です。
具体的には、次のようなことが変わります。
- 他社製アプリストアの利用が可能に:App Store以外からもアプリをダウンロードできるようになる
- ブラウザエンジンの選択肢拡大:iPhoneでもSafari以外のエンジンが使えるようになる
- 決済システムの自由化:Apple Pay以外の決済方法も選択可能になる
- デフォルト設定の変更容易化:検索エンジンやブラウザを簡単に変更できるようになる
一見すると「選択肢が増えて良いことじゃない?」と思えますよね。でも、実際はそう単純な話ではないんです。
もちろん、これらの変化がすべて悪いわけではありません。選択肢の拡大や競争促進は、場合によってはユーザーにメリットをもたらすこともあります。しかし、EUの事例を踏まえると、日本でも同じような問題が起こる可能性は十分にあると考えています。
iPhoneユーザーへの深刻な影響:「欧州化」で失われる便利さ
スマホ新法の影響を最も深刻に受けるのは、間違いなくiPhoneユーザーです。今まで「何も考えなくても安全で便利」だったiPhoneの環境が、法律により根本的に変わってしまいます。EUで既に起きている現象が日本でも始まろうとしているのです。
App Storeの独占体制が崩壊
これまでiPhoneでは、Appleが厳しく審査したアプリだけがApp Storeに並んでいました。でも、スマホ新法により第三者ストアやサイドローディング(App Store以外からの直接インストール)が解禁されます。これのメリットとデメリットは次のとおりです。
メリット
- アプリの選択肢が増える
- 手数料競争で価格が下がる可能性
デメリット(こちらの方が深刻)
- Appleの厳しい審査を通らない危険なアプリが流通
- マルウェアや詐欺アプリのリスクが急増
- どのストアが安全なのか判断が困難に
Apple製品間の連係機能に制約:普段使っている機能が続々と制限される
ここが一番痛いところです。Apple製品を選ぶ理由の一つだった「シームレスな連係機能」が「自社優遇」として規制対象になってしまいます。
日本国内の法律でどの機能がどこまで規制されるかは、今後決まる政令や公正取引委員会のガイドライン次第ですが、規制対象となる可能性が指摘されている機能は次のとおりです。
AirDrop(ファイル共有)
iPhone、Mac、iPadで写真や書類を瞬時に共有できるこの機能は、多くの人が日常的に使っているAppleの代表的な便利機能です。
しかし、他社デバイスに同じ便利さを提供していないため「自社優遇」とみなされる可能性があります。制限されると、家族や同僚との写真共有、会議資料の受け渡しなどが一気に面倒になり、LINEやメールに頼らざるを得なくなってしまいます。
AirPodsの自動切り替え・自動接続
耳に入れるだけでiPhone、Mac間で自動接続し、使用デバイスを自動で切り替えてくれる機能です。他社製イヤホンには提供されない独自連携のため、規制対象になる可能性が高いです。
この機能が制限されると、AirPodsユーザーは手動でBluetooth接続を切り替える必要が生じ、「AirPodsを選ぶ意味」が大幅に減少してしまいます。
ハンドオフ機能
iPhoneで見ていたWebページやメールをMacで続きから開ける機能で、在宅ワークや勉強で重宝している人も多いでしょう。Apple独自のエコシステム機能で競合他社を排除しているとみなされ、規制される可能性があります。
制限されると、URLを手動でコピー&ペーストしたり、ブックマークを使ったりと、作業効率が大幅に低下することになります。
ユニバーサルクリップボード
iPhoneでコピーしたテキストをMacでそのまま貼り付けられる機能は、文書作業をする人には欠かせない機能です。Apple製品間でのみ動作する排他的機能として問題視される可能性があります。
この機能が使えなくなると、テキストの受け渡しのためにメモアプリやメールを経由する必要が生じ、作業のテンポが大幅に悪化してしまいます。
iPhone通話のMac・iPad連係
iPhoneにかかってきた電話をMacやiPadで受けられる機能は、テレワーカーには特に重要な機能でしょう。他社製デバイスには開放されていない独自機能として規制対象になる可能性があります。
制限されると、大画面で作業中でも必ずiPhoneを取りに行く必要が生じ、web会議中の急な電話対応などが非常に不便になります。
写真・メモの自動同期機能
iPhoneで撮った写真が自動でMacやiPadに表示される機能は、ほぼ全てのAppleユーザーが当たり前に使っている基本機能です。iCloud経由の自動連携が他社クラウドサービスより優遇されているとして問題視される可能性があります。
この機能が制限されると、写真の整理や編集作業が格段に面倒になり、手動でのアップロード・ダウンロード作業が必要になってしまいます。
よく行く場所の履歴・最適ルート提案
行動パターンを学習して最適なルートや出発時刻を提案してくれる機能は、通勤・通学で重宝している機能です。Apple Maps独自機能で他社地図アプリを不利にしているとして規制される可能性があります。
制限されると、毎回手動でルート検索をする必要が生じ、渋滞回避や時間短縮の恩恵を受けられなくなってしまいます。
なぜこんなことが起きるの?
この法律の論理は「他社に同じ機能を提供しないなら、自社でも使っちゃダメ」というものです。でも、これって「Apple製品を買ったからこその便利さ」を否定することでしかないんですよね。
結果として、「みんなが不便になる平等」が生まれてしまいます。
確かに、規制には市場を健全化する狙いもあり、一部では利便性向上や価格低下といった恩恵も期待されています。ただ、それ以上に不便やリスクが拡大する可能性が高いのです。そもそも後述するEUの事例を見るとその懸念がわかってもらえると思います。
ブラウザ・決済システムの自由化による混乱
これ以外にも、今まで統一されていたシステムが分裂することで、安全性の担保が困難になる可能性が高いです。
ブラウザエンジンの自由化による青少年保護機能の破綻
現在のiPhoneはWebKitという統一されたブラウザエンジンを使用しており、これによって有害サイトのフィルタリングが効果的に機能しています。しかし、競争促進のためにChrome独自のBlinkエンジンやFirefoxのGeckoエンジンなど、他社製ブラウザエンジンの使用が義務付けられる予定です。
この変更により、今まで機能していたWebKitベースのフィルタリング機能が動作しなくなってしまいます。お子さんがいるご家庭では、今までのように「iPhoneだから安心」とは言えなくなり、ブラウザごとに個別のフィルタリング設定が必要になったり、そもそも対応していないブラウザでは保護機能が一切働かなくなったりする可能性があります。
決済システムの多様化による新たなリスク
アプリ内課金では、今まで安全性が確保されたApple Payシステム以外の決済方法も選択可能になります。競争により手数料は下がる可能性がありますが、聞いたことのない決済サービスや海外の怪しい決済システムが混入するリスクが高まります。
特に高齢者や決済システムに詳しくない方にとっては、どの決済方法が安全なのか判断が困難になります。詐欺業者が「手数料が安い」「お得なポイント還元」などと謳って偽の決済システムを提供し、クレジットカード情報や個人情報を騙し取る手口が横行する可能性があります。また、決済トラブルが発生した際の責任の所在も複雑になり、泣き寝入りするケースが増えるかもしれません。
Androidユーザーへの影響:すでに自由だったものがさらに複雑に
「Androidは元々自由だから関係ない」と思っていませんか?実は、その「慣れ」こそが最も危険な落とし穴なのです。今回の法律により、既存の自由度がさらに拡大する一方で、管理すべきリスクも格段に増加してしまいます。
既存の自由度がさらに拡大することの落とし穴
Androidはもともとサイドローディングが可能で、Google Play以外のアプリストアも利用できました。しかし、今回の法律でサードパーティアプリストアの利便性がさらに向上し、Google Play以外の課金システムも使いやすくなる予定です。
一見するとAndroidユーザーにとっては良いことのように思えますが、実際には管理すべきリスクが大幅に増加することになります。今まで「なんとなく安全」だったGoogle Playストア以外にも、審査基準の異なる複数のストアが乱立し、どれが信頼できるのか判断がより困難になってしまいます。
新たなセキュリティ課題と「慣れ」の危険性
Androidユーザーは既にサイドローディングや非公式アプリストアの利用に慣れているため、「今までと同じだから大丈夫」と考えがちです。しかし、この経験への過信が、実は最も危険な盲点になってしまうのです。
審査基準のバラつきによる危険アプリの増加
Google Playでは一定の審査基準がありましたが、サードパーティストアでは審査が甘かったり、そもそも審査がなかったりするケースが増えます。「Androidは元々自由だから大丈夫」という油断が最も危険で、悪質なアプリや偽アプリが堂々と配布される可能性が高まります。
特に問題なのは、Androidユーザーの多くが「APKファイルの直接インストール」や「提供元不明のアプリ」に慣れているため、危険なアプリに対する警戒心が薄くなっていることです。この「慣れ」を悪用して、本格的なマルウェアや個人情報窃取アプリが広まるリスクが非常に高いのです。
Google Play Protectだけでは対応しきれない複雑化
Googleのセキュリティ機能であるGoogle Play Protectは、主にGoogle Play経由のアプリを対象としています。しかし、複数のサードパーティストアが普及すると、すべてのアプリを監視することが技術的に困難になります。
結果として、ユーザー自身がより高度なセキュリティ知識を身につけ、アプリの提供元や権限設定を厳しくチェックする必要が生じます。しかし、一般ユーザーにとってこれらの判断は非常に難しく、結果的に「知らないうちに危険なアプリを使っている」状態が増えてしまう可能性があります。
「競争促進」の建前と現実のギャップ
政府や推進派が掲げる「消費者のための競争促進」というのは、一見美しいスローガンではあります。しかし、そんなものは建前でしかありません。
実際に先行して導入したEUの事例を見ると、建前と現実の間には大きな乖離があることがわかります。少なくとも、EUの実態を見れば、ユーザーのためのものではないことは明確です。
役所が言う「目的」
役所や推進派の論理は次のとおりです。
- 巨大IT企業による市場独占の打破
- 開発者に多様な選択肢を提供
- 消費者利益の確保
- 手数料の引き下げによる価格低下
聞こえはいいですよね。でも、本当にユーザーのためになるでしょうか?
EUの失敗例が示す現実
実は、同じような法律(DMA:デジタル市場法)がEUで既に施行されています。結果はどうだったか?1年経過後の厳しい現実は次のとおりです。
新しい革新的なアプリはほとんど登場せず
「競争が促進されれば革新的なアプリが生まれる」という期待がありましたが、実際にはそのような成果は見られませんでした。既存の大手企業以外で注目を集める新しいサービスはほとんど登場せず、むしろ小規模な開発者は複雑化したルールに対応するのに精一杯で、イノベーションに集中できない状況が続いています。
セキュリティリスクが大幅に増加
App StoreやGoogle Playの厳格な審査を経ない第三者ストアが普及した結果、マルウェアや個人情報を盗むアプリの報告件数が急増しました。特に高齢者や技術に詳しくないユーザーが被害に遭うケースが多発し、社会問題となっています。また、複数のストアが乱立することで、どこが安全なのか一般ユーザーには判断が困難な状況が生まれています。
オンラインカジノアプリなど、従来なら審査で弾かれるアプリが堂々と流通
Apple StoreやGoogle Playでは厳しく規制されていたオンラインカジノ、パチンコ・スロット系ギャンブルアプリ、アダルトコンテンツなどが、審査の甘い第三者ストア経由で大量に流通するようになりました。同じことが起こるとすると、日本では法的にグレーゾーンのオンラインカジノアプリが「ゲームアプリ」として偽装配布される可能性が高く、ギャンブル依存症の拡大や多重債務問題の深刻化が懸念されます。
最も深刻な問題は、一般ユーザーが知らないうちに違法行為に手を染めてしまうリスクです。日本では賭博罪により、オンラインカジノでの賭博行為は違法とされていますが、多くの人がその事実を知らずにアプリをダウンロードし、「ただのゲーム」だと思って遊んでいるうちに、気づかないまま犯罪行為を行ってしまう可能性があります。また、これらのアプリは「お小遣い稼ぎアプリ」や「ポイントアプリ」と偽って配布されることも多く、違法性を隠蔽した形で一般に広まる危険性が高いです。
さらに深刻なのは、青少年がこれらのアプリに容易にアクセスできるようになることです。未成年者が知らずに違法ギャンブルに参加してしまい、後になって法的な問題に巻き込まれるリスクや、早期からギャンブル依存症に陥ってしまう可能性もあります。保護者も「普通のゲームアプリ」だと思い込んで見過ごしてしまい、家族全体が知らないうちに法的リスクを抱えることになりかねません。
ユーザーの満足度は向上せず、むしろ低下
期待された「手数料削減」や「価格競争」の恩恵を実感できるユーザーは少なく、むしろアプリの選択肢が増えすぎて迷うことが多くなったという声が目立ちます。また、今まで使えていた便利な機能が「自社優遇」として制限されたことで、多くのユーザーが不便さを感じています。セキュリティ面での不安も相まって、「以前の方が良かった」と感じるユーザーが多数を占める状況です。
「競争促進」という美名のもとに始まったEUの実験は、決して成功とは言えない状況です。
本当の狙いは何なのか?
正直なところ、この法律は「ユーザーのため」というより、「政治的な意図」や「世界的な規制潮流への対応」という側面が強いように感じられます。
大企業への規制は確かに必要な場面もありますが、その結果としてユーザーが不利益を被るのは本末転倒ですよね。最近の行政はこのようなことばかりやっていて、本当に辟易です。
【警告】メディアやインフルエンサーの「スマホ新時代」キャンペーンを疑え
法律施行が近づくにつれて、政府や関連企業と連携したメディアやインフルエンサーによる「ポジティブキャンペーン」が本格化する可能性が非常に高いです。美しい言葉で飾られた宣伝に騙されないように注意したいところです。
政府主導のポジティブ広報に要注意
2025年12月の法律施行に向けて、政府や関連省庁から「デジタル新時代の幕開け」「競争促進で消費者メリット拡大」といったポジティブなメッセージが大量に発信される可能性が非常に高いです。これまでも日本政府は新しい法律や制度の導入時に、メリット面だけを強調した広報活動を積極的に展開してきた実績があります。
特に危険なのは、政府の意向を受けたインフルエンサーや主要メディアが次のように一方的なポジティブ情報を拡散することです。若年層やデジタルに詳しい層をターゲットに、まるで「革新的な改革」であるかのように演出される可能性があります。
具体的に警戒すべき表現
- 「スマホの未来が変わる」「新時代の始まり」
- 「Apple・Googleの独占が終わり、自由な選択が可能に」
- 「アプリが安くなる」「手数料削減でユーザーメリット」
- 「イノベーション促進で日本のIT業界が活性化」
これらの表現を見かけたら、まず「誰がその情報を発信しているのか」「政府や大企業との関係はないか」を疑ってください。また、このような発言に対する明確な根拠は示せていないと思います。そういうものは「宣伝」だと思ってしまって問題ないと思います。
ステマ規制があっても信用できない理由
現在はステルスマーケティング規制により「広告」「提携」の明示が義務付けられていますが、官民連携の「啓発活動」や「情報提供」という名目であれば、実質的な広告でもその表示義務を回避できる場合があります。
そのため、次のようなパターンについては十分に注意したいです。
- 政府機関や関連団体からの「情報提供」として発信される内容
- 「デジタル推進」「DX促進」などの名目で行われるキャンペーン
- 有名インフルエンサーが「個人的な意見」として投稿するポジティブ情報
- IT系メディアの「解説記事」という形で掲載されるメリット偏重記事
これらは形式的には広告ではないため、批判的な視点や問題点への言及が意図的に省かれている可能性があります。
EUで実際に起きた「期待→失望」パターン
EUのDMA(デジタル市場法)施行時にも、政府と連携するメディアやインフルエンサーが「公平な競争実現」「ユーザーの自由拡大」を謳う大規模なポジティブキャンペーンを展開しました。当初は多くの人が「素晴らしい改革」として期待していたのです。
しかし、実際に法律が施行されると、技術系の専門家やユーザーコミュニティから「予想外の不便」「セキュリティ低下」「期待していたメリットが実現しない」といった批判的な声が相次ぎました。結果として、公式広報の内容と現実のギャップが明らかになりました。
EUで実際に起きた問題には、次のようなものがあります。
- 便利だった機能が「自社優遇」として制限された
- セキュリティリスクが想定以上に増加した
- 新しい革新的なアプリやサービスはほとんど登場しなかった
- ユーザーの満足度は向上しなかった
日本でも必ず起きる「トーン変化」
EUの経験から予想されるのは、日本でも同じパターンが繰り返されることです。まず政府主導の「スマホ新時代」キャンペーンが展開され、多くのメディアやインフルエンサーがポジティブな情報を発信します。
しかし、実際に法律が施行され、ユーザーが不便さやリスクを体感するようになると、今度は同じメディアやインフルエンサーが「実は問題があった」「予想外の事態」「対策が必要」といった論調に急速に転換することが予想されます。
トーン変化の典型例
- 施行前:「選択肢拡大で便利になる」
- 施行後:「セキュリティ対策の重要性」
- さらに後:「制度の見直しが必要」
はっきり言えば、一部のメディアやインフルエンサーは、その時々で都合のいいように掌をくるくる回転させる無責任な人たちです。そして行政も一切の責任を取ることのない無責任な組織です。
法律は施行されてしまえば、結局被害を受けるのは一般のユーザーだけです。しかし、後述するとおり、声をあげる手段はまだ残されています。
信頼できる情報源の見分け方
ポジティブな発言を見かけたら、ほとんどは疑った方がいいでしょう。その中でも、次のような発信には注意したいところです。
疑うべき情報発信者
- 政府機関と密接な関係がある組織・個人
- IT業界の大企業とタイアップが多いインフルエンサー
- 過去に政府の政策を無批判に賞賛してきたメディア
- メリットばかりを強調し、リスクに言及しない専門家
比較的信頼できる情報源
- EUの実例を踏まえてリスクも含めて論じている専門家
- 政府や大企業との利害関係が薄い独立系の技術者・研究者
- ユーザー目線でのデメリットも正直に指摘しているメディア
- セキュリティ専門家による客観的な分析
ユーザー自身が判断の基準を持とう
最も重要なのは、誰かの意見に盲従するのではなく、あなた自身が判断の基準を持つことです。「選択肢が増える」「競争が促進される」といった美しい言葉に惑わされず、「本当に自分にとってメリットがあるのか?」「失うものとのバランスはどうか?」を冷静に考えてください。
自分で判断する際のポイントは次のとおりです。
- メリットだけでなく、デメリットや制約も必ず確認する
- EUなど先行事例の「現実」を調べる
- 発信者の立場や利害関係を確認する
- 「お得」「便利」という感情に訴える表現に注意する
- 家族や身近な人への実際の影響を具体的に想像する
政府やメディアが「国民のため」と言っても、それが本当にユーザーのためになるとは限りません。特にスマホ新法のように、日常生活に直結する法律については、他人の意見ではなく、自分自身の判断で行動することが最も重要です。
今からユーザーができること
スマホ新法のパブリックコメントは、2025年6月13日に終了しています。一般消費者への周知は限られており、パブコメ募集終了を大々的にニュースやSNSで拡散する動きはほとんど見られなかったので、「いつやっていたのかわからなかった」「気づいたら終わっていた」と感じるような状況ではあります。
このような状況ですが、ユーザーの声を届ける方法は複数あります。諦める必要はありません。
議員・行政への直接的な働きかけ
地元選出の国会議員や内閣府、公正取引委員会に直接メールや書面で意見を送ることができます。各機関の公式ホームページには「ご意見フォーム」や問い合わせ窓口が設置されており、一般市民からの意見を受け付けています。「便利さと安全性を犠牲にしてまで必要な法律なのか」という素朴な疑問でも構いません。多くの声が集まれば、必ず影響力を持ちます。
SNS・ブログ・動画での発信活動
XやInstagram、YouTube、TikTokなどを活用して、一般ユーザーとしての率直な意見や懸念を発信しましょう。「#スマホ新法」「#iPhone制限反対」などのハッシュタグを使うことで、同じ関心を持つ人たちとつながることができます。個人の体験談や「この機能が使えなくなったら困る」という具体的な声は、政治家やメディアにとって非常に価値のある情報です。
メディア・市民団体への情報提供
消費者団体や技術系メディアの記者に対して、ユーザー目線での問題意識や現場の実態を伝えることも効果的です。記者は常に「生の声」を求めているため、ユーザーの体験や懸念が記事になり、より大きな議論に発展する可能性があります。特に「子どもの安全が心配」「高齢の親が騙されそう」といった身近な問題は、多くの人の共感を呼びます。
オンライン署名・キャンペーンの活用
Change.orgなどのプラットフォームを使って署名活動やキャンペーンを展開することで、世論や行政に対するインパクトを生み出すことができます。「スマホ新法の安全性検証を求める署名」「iPhone制限の見直しを求める署名」など、具体的でわかりやすいテーマで署名を募ることで、多くの賛同者を集められる可能性があります。
行政の透明性を求める活動
パブリックコメントの結果がどのように法律に反映されたのか、どのような意見が寄せられたのかを情報開示請求で明らかにし、その内容を市民目線で検証・公開する活動も重要です。行政が本当にユーザーの声を聞いているのか、利用者不在の議論になっていないかを監視することで、より良い制度設計を促すことができます。
まとめ:「便利さ vs 安全性」から「自己責任時代」へ
ここまで解説してきたように、スマホ新法は明らかにユーザーに対するデメリットが大きい法律です。
「競争促進」「消費者利益の確保」「選択肢の拡大」という建前はあるものの、 EUの失敗例が示すように、ユーザーメリットは限定的で、リスクの方が大きいのは明確。iPhoneはこれまでの安全性と利便性が失われ、Androidはセキュリティリスクがさらに拡大してしまうでしょう。
特に深刻なのは、今まで「何も考えなくても安全」だったスマートフォンの環境が根本から変わってしまうことです。AirDropやAirPodsの便利な連携機能が制限され、サードパーティストア経由で危険なアプリや違法ギャンブルアプリが流通し、青少年保護機能も破綻してしまいます。
政府やメディアが「新時代の幕開け」と美化しようとも、実際に不便さやリスクを被るのは私たち一般ユーザーです。EUの失敗を繰り返さないためにも、今こそユーザーの立場から「本当に必要な法律なのか?」を問い直す声をあげるべきだと思います。
もし可能なら、この記事の内容を周りの人にシェアしてください。家族、友人、同僚との会話のきっかけにしていただければ幸いです。声が広がれば広がるほど、法律の内容が改善される可能性があります。
みなさんのスマートフォンライフがより良いものになるよう、一緒に考えていきましょう。
主な問い合わせ先
公正取引委員会(所管・指針、公表・指定、運用全般)
- 御意見・御要望フォーム:https://www.jftc.go.jp/soudan/tetsuzuki/goiken.html
- 相談・申告・情報提供・手続等 窓口(総合案内):https://www.jftc.go.jp/soudan
- インターネットによる申告(独禁法違反等の申告):https://www.jftc.go.jp/soudan/denshimadoguchi/index.html
- 情報提供フォーム(一般の情報提供):https://www.jftc.go.jp/partnership_package/index/form.html
- 独占禁止法違反のオンライン申告フォーム直通:https://www.jftc.go.jp/soudan/shinkoku/online_shinkoku.html
経済産業省(ガイドライン、開発者向け案内等)
- ご意見・お問合せフォーム(本省):https://mm-enquete-cnt.meti.go.jp/form/pub/honsyo03/meti_toiawase
- パブリックコメント案内(METI内の案内ページ):https://www.meti.go.jp/feedback/
- 参考:アプリ開発者向け「スマホソフトウェア競争促進法のガイドライン等」総合ページ:https://www.app-developers.meti.go.jp/announcement_14/
デジタル庁(デジタル政策全般)
- お問い合わせ(該当する一般窓口がないため、関連ページ例):デジタル推進委員 問合せ先掲載ページ https://www.digital.go.jp/policies/digital_promotion_staff
- 参考:個別プロジェクト用の問い合わせページも多数あります。
総務省(行政相談・ICT関連)
- インターネットによる行政相談受付(行政評価局):https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/hyouka/soudan.html
- 関東総合通信局 総合通信相談所 メール相談フォーム(地域の通信相談窓口例):https://www.soumu.go.jp/soutsu/kanto/ques/faq/attention/index.html
e-Gov(パブリックコメント)
- e-Gov パブリック・コメント トップ(案件検索):https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTLIST&Mode=1
- 参考:過去の案件・結果公示は案件一覧で検索できます