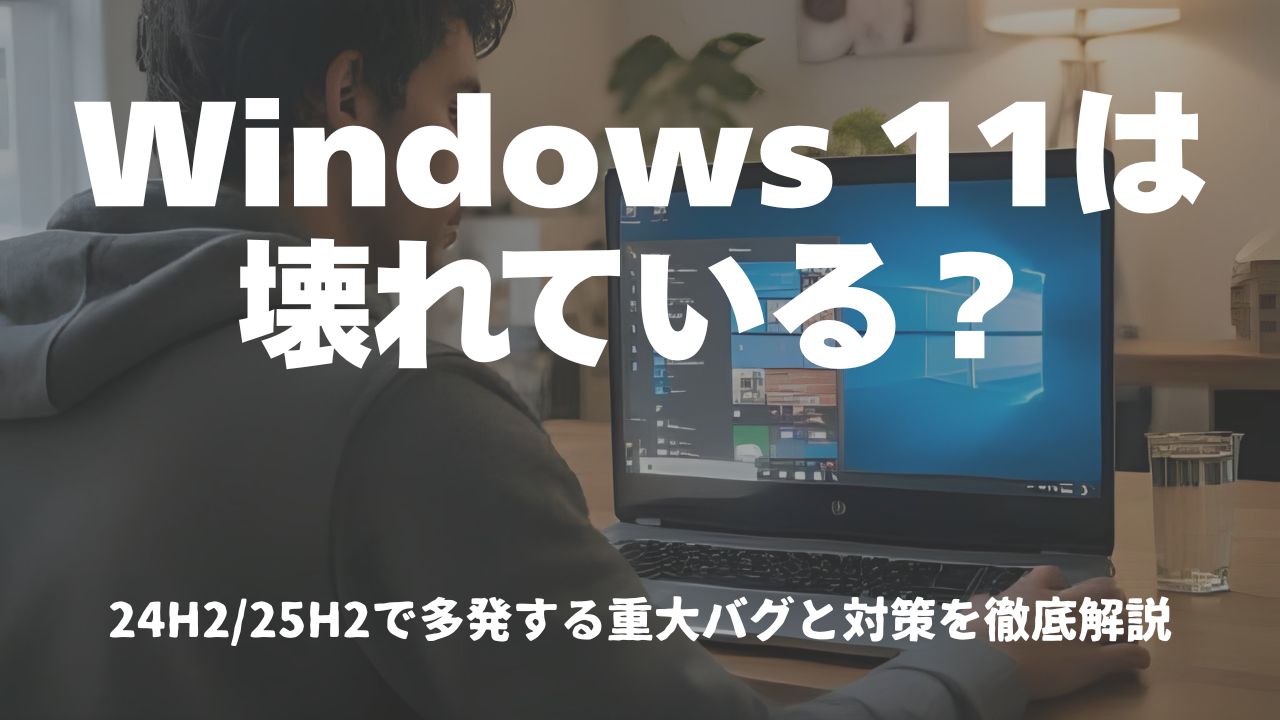2024年秋にリリースされたWindows 11の大型アップデート「24H2」。実はこのアップデート、リリース直後から「OSの根幹が壊れている」とまで言われるほどの深刻な不具合が多発しているのは有名な話。
エクスプローラーが開かない、スタートメニューが反応しない、タスクバーがフリーズする——。こうした基本的な操作ができなくなるトラブルが世界中で報告され、Microsoft自身も公式に「コア要素の障害」を認める事態になっています。
さらに困ったことに、この24H2を基盤として開発された次期バージョン「25H2」(2025年秋リリース)にも、同じ問題が引き継がれてしまっているんですよね。つまり、現在進行形でWindowsアップデートの不具合に悩まされる状況が続いているということです。
そこで、Windows 11 24H2/25H2で発生している不具合の詳細と、その背景にある技術的な問題、そしてユーザーができる対処法について、わかりやすく解説していきます。
どんな不具合が起きているのか?
まずは、実際にどのような症状が報告されているのか見ていきましょう。
OSの基幹部分が動かなくなる
最も深刻なのが、Windowsの基本操作に関わる部分での障害です。エクスプローラー、スタートメニュー、タスクバーといった、毎日使う機能が突然使えなくなってしまいます。
具体的には次のような症状が報告されています。
- エクスプローラーが起動しない、またはフリーズする:ファイル操作ができず、作業が完全にストップしてしまう
- スタートメニューが開かない:アプリの起動やシャットダウンすらできない状態に
- タスクバーが反応しない:開いているアプリの切り替えができなくなる
- 設定画面が表示されない:システム設定の変更ができず、トラブルシューティングも困難に
- 通知センターが機能しない:重要な通知を見逃すリスクが発生
これらの症状が同時に起きると、もはやパソコンとして使い物にならない状態になってしまいます。
アップデート関連のトラブル
アップデート作業そのものに関する問題も多発しています。
- アップデートのインストールが失敗する:何度試してもエラーで完了しない
- アップデート後にログインできなくなる:画面が真っ黒のまま、またはログイン画面でフリーズ
- Windows回復環境(WinRE)でUSBデバイスが使えない:システム復旧ツールが使えず、トラブル対応が不可能に
特にWinREでのUSBマウス・キーボード無反応問題は深刻です。パソコンに問題が起きたときの「最後の砦」である回復環境で操作できないというのは、本当に困ります。
ハードウェアやパフォーマンスへの影響
一部のユーザーからは、ハードウェアに関連する問題も報告されています。
- SSDの認識不良や速度低下
- システム全体のパフォーマンス低下
- 特定のアプリケーションとの互換性問題
これらの症状について、Microsoftは公式の「Release Health」ページで随時情報を更新しています。自分のパソコンで気になる症状がある場合は、まずこのページを確認してみるといいでしょう。
なぜこんなに大規模な不具合が起きているのか?
ここまで広範囲に問題が発生した背景には、Windows 11 24H2での大規模な設計変更があります。
UIシステムの根本的な刷新
Windows 11 24H2では、ユーザーインターフェース(UI)の基盤部分が大きく刷新されました。具体的には、「XAML」というUI技術をベースにした新しいシェルシステムが導入されたんです。
この変更自体は、より現代的で使いやすいインターフェースを実現するための前向きな取り組みでした。しかし、OSの根幹部分を大きく変更したことで、予期せぬ問題が次々と発生してしまったようです。
技術的には、次のような問題が指摘されています。
- 初期化処理の競合:システム起動時に複数の処理が同時に走り、お互いに干渉してしまう
- タイミング依存のバグ:特定の条件が重なったときだけ発生する不具合で、テスト段階では発見が難しい
- 互換性の問題:既存のシステムやアプリとの連携がうまく機能しない
24H2と25H2の密接な関係
さらに厄介なのが、次期バージョン「25H2」も24H2と実質的に同じコードベースで開発されているという点です。
つまり、24H2で発生している根本的な設計上の問題が、そのまま25H2にも引き継がれてしまっているんですよね。25H2は24H2の改良版という位置づけですが、基礎部分が共通しているため、未修正のバグも多く残っているというわけです。
これは、今後のWindowsアップデートに対しても不安を感じざるを得ない状況と言えます。
Microsoftの公式対応は?
では、Microsoft側はこの問題にどう対応しているのでしょうか。
公式に問題を認めている
まず、Microsoftは今回の不具合を正式に認め、「コア要素の障害」として公開しています。過去には問題を曖昧にしたり、対応が遅れたりすることもありましたが、今回は比較的早い段階で認識を示しました。
公式の「Windows 11 Release Health」ページでは、既知の問題として以下のような情報が随時更新されています。
- どのような症状が報告されているか
- 影響を受けるシステムの条件
- 現在の調査状況
- 利用可能な回避策
修正パッチの継続的な配信
Microsoftは月例の累積更新プログラム(累積アップデート)を通じて、段階的に修正を進めています。いくつかの不具合については暫定的な対策も公開されていますね。
ただし、2025年11月時点では、すべての問題が解決されたわけではありません。一部の不具合は修正されましたが、根本的な設計に関わる問題については、まだ完全な解決に至っていないのが現状です。
「決定的な対処法はない」との見解
困ったことに、Microsoft自身が「ユーザー側にできる決定的な対処法は現状ない」という見解を示しています。つまり、特定の設定変更や操作で確実に解決できる方法は、今のところ存在しないということです。
これは正直に状況を伝えているとも言えますが、ユーザーとしては不安が残りますよね。当面は、Microsoftからの修正プログラム配信を待つしかないというのが実情です。
23H2サポート終了という「逃げ場のない」状況
さらに問題を深刻にしているのが、Windows 11 23H2のサポートが既に終了しているという事実です。
つまり、ユーザーには実質的に選択肢がありません。セキュリティ更新を受け続けるためには、不具合だらけの24H2/25H2にアップデートするしかなく、「問題が解決されるまで待つ」という選択肢が取れない状況になっています。
つまり、ユーザーとしては、
- 不具合を抱えた24H2にアップデートしてトラブルに巻き込まれるリスク
- 23H2に留まってセキュリティ更新を受けられないリスク
この二択を迫られているわけです。どちらを選んでも問題があるという、まさに「詰んでいる」状態と言えます。これは非常に理不尽な話ですよね。
本来であれば、新バージョンが安定するまで旧バージョンのサポートを延長するなど、ユーザーに配慮した対応があってしかるべきでした。しかしMicrosoftは、24H2の深刻な不具合が明らかになった後も、23H2のサポート延長などの措置を取っていません。
こうした対応は、「ユーザーの利便性よりもリリーススケジュールを優先している」という批判を招いても仕方がないでしょう。
ユーザーができる現実的な対処法
完全な解決策がないとはいえ、トラブルのリスクを減らしたり、被害を最小限に抑えたりする方法はあります。
前述の通り、23H2のサポートが終了しているため、セキュリティ面を考えると24H2/25H2への移行は避けられません。しかし、少しでもリスクを下げるために、次のような対策を講じるのがおすすめです
Windows Updateを慎重に扱う
最も基本的な対策は、アップデートを急がないことです。
アップデートの一時停止
設定アプリから「Windows Update」を開き、「更新の一時停止」を選択すれば、最大5週間までアップデートを保留できます。新しいアップデートがリリースされた直後は、様子を見てから適用するのが賢明でしょう。
ただし、セキュリティ更新も含まれているため、あまり長期間停止するのはリスクがあります。1〜2週間様子を見て、大きな問題が報告されていなければ適用する、というバランスが大切です。
すでにアップデート済みで問題が発生している場合
もし、深刻な不具合に遭遇している場合は、次の方法を試してみてください。
- システムの復元ポイントを利用する:アップデート前の状態に戻せる可能性があります
- セーフモードで起動する:最小限の機能だけで起動することで、トラブルシューティングしやすくなります
- 特定の更新プログラムをアンインストールする:問題の原因となっているアップデートを削除できます
バックアップと復旧の準備
万が一に備えて、定期的にバックアップすることは不可欠です。
- 重要なデータの定期的なバックアップ:外付けストレージやクラウドストレージに保存
- システムイメージの作成:OS全体を丸ごとバックアップ
- 回復用USBメディアの作成:システムが起動しなくなった場合の最終手段
これらの準備があれば、最悪の場合でもデータを失わずに済みます。「備えあれば憂いなし」という言葉がぴったりですね。
Windowsユーザーが大量にLinuxへ?Zorin OSの急増
実は今、Windowsの不具合を避けるために、一時的にLinuxに移行するユーザーが急増しています。特に「Zorin OS」というLinuxディストリビューションが注目を集めています。
Zorin OS 18が1ヶ月で100万ダウンロード
2024年秋から2025年にかけてリリースされた「Zorin OS 18」は、リリースからわずか1ヶ月で100万ダウンロードを達成しました。これはZorin OSの歴史上、最大規模のヒットです。
さらに驚くべきは、ダウンロードユーザーの78%がWindowsからの流出ユーザーだという点。つまり、Windows 11の不具合に嫌気がさしたユーザーが、代替OSとしてZorin OSを選んでいるんですね。
なぜZorin OSが選ばれているのか
Linuxというと「難しそう」「初心者には無理」というイメージを持つ方も多いかもしれません。しかしZorin OSは、そんなイメージを覆すLinuxです。
Windowsライクな操作感
Zorin OSの最大の特徴は、Windowsに似たユーザーインターフェースを採用している点です。スタートメニューやタスクバーの配置がWindowsとほぼ同じなので、乗り換えてもほとんど違和感なく使えます。
高い互換性と軽快な動作
Zorin OSには「WINE」という技術が組み込まれていて、多くのWindowsアプリケーションをそのまま実行できます。完全な互換性というわけではありませんが、日常的に使う主要なソフトの多くは問題なく動作するようです。
また、Windowsに比べてシステムが軽量なため、古いパソコンでも快適に動くという利点もあります。Windows 11のシステム要件を満たせないパソコンでも、Zorin OSなら現役で使い続けられるんですよね。
世界的な話題に
この「WindowsからLinuxへの大移動」は、海外メディアでも大きく報道されました。特に技術系のニュースサイトでは「Microsoftの自滅」「ユーザーの反乱」といった見出しで取り上げられています。
もちろん、すべてのWindowsユーザーがLinuxに移行するわけではありません。しかし、大手IT企業であるMicrosoftが提供するOSから、オープンソースの代替OSへとユーザーが流れているという事実は、業界に大きな衝撃を与えています。
ただしまったく同じように使えるわけではない
ここまでは明るい話題でしたが、Zorin OSがWindowsライクだからといって、Windowsとまったく同様に使えるというわけではありません。OSが持つクセが違うので、使えば使うほど「Windowsでできたことができない」と思うことも出てきます。
やはり操作性やファイルシステムには違いがありますし、アプリの互換性も完全ではないので、あまり過剰な期待は禁物。実際使ってみたけど思うように使えなくてやめたという人も少なくありません。
新しいOSの操作を覚えるつもりがないと、やはり厳しい部分はあるでしょう。ただし、Zorin OSの使い方をある程度マスターできれば、フレキシブルに使えるようになるので、大きな強みになります。
開発者や専門家からの批判
Windows 11 24H2/25H2の問題は、開発コミュニティでも大きな批判を呼んでいます。
タスクマネージャー開発者の痛烈な批判
特に注目されたのが、Windowsの「タスクマネージャー」の開発者による発言です。彼はSNS上で、今回の不具合について「設計プロセスと品質管理の根本的な問題」と指摘しました。
具体的には、次のような問題点を挙げています。
- テスト期間の不足:十分なテストを行わないまま製品版をリリースしている
- ユーザーフィードバックの軽視:ベータテストで報告された問題を無視している
- 短期的な開発サイクルの弊害:定期的なアップデートスケジュールを優先するあまり、品質が犠牲になっている
内部事情を知る立場からの批判だけに、説得力がありますね。
企業姿勢への疑問
一部の専門家からは、Microsoftの企業姿勢そのものを問題視する声も上がっています。
「ユーザーをベータテスターとして扱っている」「製品版でも実質的に未完成」といった指摘は、残念ながら的を射ていると言わざるを得ません。
特に批判が集中しているのが、23H2のサポートを終了しながら、不具合だらけの24H2/25H2への移行を事実上強制しているという点です。IT系メディアやセキュリティ専門家からは、「ユーザーに選択肢を与えない強権的な対応」「品質管理の失敗をユーザーに押し付けている」といった厳しい意見が相次いでいます。
かつてWindowsは、安定性と信頼性を誇るOSでした。しかし近年は、アップデートのたびに何かしらの問題が発生するという状況が続いています。今回の24H2/25H2の問題は、その集大成とも言える事態になってしまったわけです。
ユーザーに求められる自衛策
専門家の多くが共通して推奨しているのが、「多層的なリスク管理」です。
- アップデート前に必ずバックアップを取る
- 新しいアップデートは即座に適用せず、数週間様子を見る
- 万が一に備えて、代替手段(別のパソコン、Linuxの起動USBなど)を用意しておく
「Microsoftが完璧な製品を提供してくれる」という前提は、もはや成り立たない時代になってしまったのかもしれません(そもそもそんな時代はなかったかもしれませんが、最近は特にひどい状況です)。ユーザー側も、自分の環境は自分で守るという意識が必要になってきています。
まとめ:今後どう付き合っていくべきか
Windows 11 24H2/25H2の不具合問題は、単なる一時的なトラブルではなく、Windowsの今後を考える上で重要な転換点と言えるかもしれません。
Windows 11は、当初からあまり評判は芳しくありませんでしたが、24H2/25H2の問題でさらに信頼を大きく損なってしまいました。
Microsoftには、ユーザーの信頼を取り戻すべく、品質管理体制の抜本的な見直しを期待したいところです(正直、難しそうな気がしますが)。そしてユーザーは、慎重に付き合っていく必要があるでしょう。